豆 知 識 ★ 雑 学 ★
====================================================
--- 目 次 ---
★上総掘り(千葉県君津市で考案された深井戸工法のこと)
--------------------------------------------------------------------------------------------
 河岸段丘が発達した千葉県君津市の小櫃川・小糸川流域では、飲料水や農業用水の確保が困難でした。江戸時代までの井戸掘りと言えば、人力で竪穴を掘る「掘り井戸」、やがて地中に鉄棒を突き入れる鉄棒式(突抜工法、掘抜工法)が普及しますが、鉄棒式で掘削できるのは深さおよそ20間(約35m)までで、充分な飲料水や農業用水を確保できません。そこで小櫃地区では大村安之助が、小糸地区では池田久吉と池田徳蔵らが中心となり、技術の改良に努めました。
河岸段丘が発達した千葉県君津市の小櫃川・小糸川流域では、飲料水や農業用水の確保が困難でした。江戸時代までの井戸掘りと言えば、人力で竪穴を掘る「掘り井戸」、やがて地中に鉄棒を突き入れる鉄棒式(突抜工法、掘抜工法)が普及しますが、鉄棒式で掘削できるのは深さおよそ20間(約35m)までで、充分な飲料水や農業用水を確保できません。そこで小櫃地区では大村安之助が、小糸地区では池田久吉と池田徳蔵らが中心となり、技術の改良に努めました。
明治15年、大村と池田久吉は鉄棒の代わりに樫の木を使う樫棒式を考案。用具の軽量化と労力の軽減が実現し、50~60間(90~110m)の掘削が5~6人で行えるようになりました。
その後、大村と池田徳蔵は竹ヒゴと掘り鉄管、スイコを組み合わせた掘削技術を考案し、
さらに200~300間(360~540m)の掘削が可能となっていきました。
 明治19年には小糸地区で、石井峯次郎がハネギを考案し、沢田金次郎がシュモクとヒゴグルマを考案したことにより、明治28年頃には現在の上総掘り技術が完成されたと言われています。
その後、上総掘りは全国に広まり、天然ガス・温泉・石油の採掘などに活用されましたが、昭和40年代には灌漑用井戸の需要減・水道の普及・機械掘りの普及などによって人件費のかかる上総掘りは行われなくなっていきました。
明治19年には小糸地区で、石井峯次郎がハネギを考案し、沢田金次郎がシュモクとヒゴグルマを考案したことにより、明治28年頃には現在の上総掘り技術が完成されたと言われています。
その後、上総掘りは全国に広まり、天然ガス・温泉・石油の採掘などに活用されましたが、昭和40年代には灌漑用井戸の需要減・水道の普及・機械掘りの普及などによって人件費のかかる上総掘りは行われなくなっていきました。
しかし近年、水不足に苦しむ途上国などで国際貢献に役立つ技術として、重機を使わずに少人数で掘れる点などが世界的に注目を集めています。
施設整備・管理のための天然ガス対策ガイドブック
施設整備・管理のための天然ガス対策ガイドブックパンフレット
東京第二営繕事務所ホームページ・天然ガス対策
★従来の光源と比較した“いつになったら元が取れるか”試算
--------------------------------------------------------------------------------------------

■ 60W形白熱電球と交換で、元が取れるのは【1年4カ月】
消費電力は実測で11Wだった。消費電力が56Wの60W形白熱電球と交換しても、明るさは落とさずに1/5の節電が可能だ。11Wという数値は、今年レビューしたLED電球の中でも最も高い消費電力となってしまうのだが、明るさ、拡散性共に60W形白熱電球とひけをとらず、密閉器具にも対応している点で、大きなアドバンテージを感じる。
初期費用にかかる電球代の元を取る期間は、約1年4カ月という試算になった。1年前後で元が取れるLED電球が多く登場してはいるが、明るく、光が広がるという“明かりの質”を考えると、そこまで悪い選択ではないだろう。
しかし、電球形蛍光灯と比較するのは現実的とは言えない。なぜなら、試算では蛍光灯を4つ目に取り替えた13年4カ月(160カ月)で、やっと初期投資額を回収する。しかし、これだとLED電球の定格寿命(毎日8時間で13年8カ月)がすぐ迫ってしまう。これは電球形蛍光灯よりも高価で、かつ消費電力もさほど変わらない点が要因だ。確かに、明るさや光色、点灯回数による寿命を受けない点で優位性はあるが、現在、まったく不満なく電球形蛍光灯を使用しているのなら、無理に取り替える必要はないだろう。
【エバーレッズ 全方向タイプ LDA11L-G 640lm】
従来の光源と比較した“いつになったら元が取れるか”試算
| 光源 |
消費
電力 |
1カ月 |
3カ月 |
半年
(6カ月) |
1年 |
1年
4カ月 |
2年
2カ月 |
4年 |
8年
|
13年
4カ月
|
エバーレッズ
全方向タイプ
640lm
|
11W |
4,039円 |
4,157円 |
4,334円 |
4,688円 |
4,924円 |
5,514円 |
6,812円 |
9,644円 |
13,421円 |
白熱電球
60W形 |
54W |
370円 |
966円 |
1,932円 |
3,792円 |
5,055円 |
8,251円 |
15,166円 |
30,332円 |
50,553円 |
白熱電球
40W形 |
37W |
269円 |
665円 |
1,329円 |
2,587円 |
3,449円 |
5,641円 |
10,348円 |
20,696円 |
34,493円 |
電球型
蛍光灯 |
10W |
1,445円 |
1,554円 |
1,719円 |
2,047円 |
2,266円 |
2,814円 |
4,018円 |
8,036円 |
14,320円 |
※表中の金額は、電球代と電気代をプラスした「維持費」 ※1日の使用時間は8時間と仮定
※白熱電球には、4カ月ごと、電球形蛍光灯は2年9カ月ごと電球代を加算する (切れた電球代の購入費として)
※電気代は1kWh=22円で計算 LED電球価格は\3,980-で計算
★七 草
--------------------------------------------------------------------------------------------

春の七草
the seven herbs of spring
せり なずな ごぎょう はこ(く)べら ほとけのざ
すずな すずしろ これぞななくさ
|
|
名 称
|
英 名
|
備 考 |
| セリ |
芹 |
Japanese parsley |
若菜は香りが良く、お浸しなどの食用に。セリ科 |
| ナズナ |
薺 |
shepherd's purse |
「ナズナ」の別名は「ペンペングサ」「シャミセングサ」。アブラナ科 |
| ゴギョウ |
御形 |
cottonweed |
「ゴギョウ」は「ハハコグサ(母子草)」のこと。「オギョウ」とも。キク科 |
| ハコベラ |
繁縷 |
chickweed |
「ハコベ」のこと。ナデシコ科 |
| ホトケノザ |
仏の座 |
Lamium amplexicaule |
現在の「ホトケノザ」ではなく、「タビラコ(田平子)」を指す。「ホトケノザ」は「シソ科」だが、「タビラコは「キク科」。 |
| スズナ |
菘・鈴菜 |
a turnip |
「カブ(蕪)」のこと。アブラナ科 |
| スズシロ |
蘿蔔・清白 |
a Japanese radish |
「スズシロナ」の略で、「ダイコン(大根)」のこと。アブラナ科 |
- 1月7日[the Seventh of January]は、「人日(じんじつ)の節句」で、この日を「七草」「七草の節句」などともいいます。
- 1月7日の朝に「七草粥」を食べる風習があります。
- 「七草粥」rice gruel containing the seven spring herbs(, eaten on the seventh day of the New Year)
- 「春の七草」は「七草粥」として食べるため、英語に訳すと『the seven herbs of spring 』ですが、「秋の七草」は観賞して楽しむ植物のため『seven flowers』と訳されます。
- 七草の風習や、その種類は地域によって違いもあるということです。
- 現在言われている七草の種類は、1362年頃に書かれたという『河海抄(かかいしょう)』という文献に見られます。
「芹 なづな 御行 はくべら 仏座 すずな すずしろ これぞ七種」
『河海抄』 : 四辻善成 著 1362年頃成立
「源氏物語」に注解・注釈を加えた大著とされる。
- 「七草粥」を食べて邪気を祓い、一年の無病息災を祈るとされる「七草」の風習は、もともと中国から伝わり、平安時代から宮中で行われていたものが、形を変えて庶民へと広まったともされています。
- 当時は七種類の穀物で作られ、「七種粥」と言われたという説もあり、入っていたものはコメ、クリ、キビ、ヒエ、ミノ、ゴマ、アズキで、「春の七草」が使われるようになったのは鎌倉時代になってからともいわれています。
- 現在の「七草粥」は、新暦の1月7日に行ったりしますが、元々旧暦の正月は今の2月頃で、そのころになると、厳しい寒さの中にも春の陽射しも感じ始め、野草も芽吹き始める頃だったのでしょう。野菜不足を補う意味もあったのでしょうか。現在の1月7日の「七草粥」は、おせち料理で疲れた胃をいたわる意味を持たせたりもしているようです。
- 「人日の節句」の「人日」は、「人の日」で、元日からそれぞれの日に獣畜を当てはめて占う風習が中国にあり、七日目が「人」で、その日を人を大切にする節句にしたともいわれ、中国の風習に日本の風習が合体したとも言われているようです。
|
秋の七草
the seven flowers of autumn
はぎのはな おばな くずはな なでしこのはな
おみなえし また ふじばかま あさがおのはな
|
|
名 称
|
英 名
|
備 考 |
| ハギ |
萩 |
(a) bushclover |
マメ科 |
| オバナ |
尾花 |
Japanese pampas grass |
ススキ(薄・芒)のこと。イネ科 |
| クズ |
葛 |
kudzu (vine) |
マメ科 |
| ナデシコ |
撫子 |
a pink |
ナデシコ科 |
| オミナエシ |
女郎花 |
Patrinia scabiosaefolia |
オミナエシ科 |
| フジバカマ |
藤袴 |
(a) thoroughwort |
キク科 |
| キキョウ |
桔梗 |
a bellflower |
キキョウ科 |
|
|
★風速の目安
--------------------------------------------------------------------------------------------

ビューフォート風力階級表
|
風
力
階
級
|
名称
|
基準説明
|
相当風速
|
|
和名
|
英語名
|
陸上
|
海上
|
[knots]
|
[m/s]
|
|
0
|
平穏
|
calm
|
静穏。煙はまっすぐに昇る。
|
鏡のような海面。
|
0-1
|
0.0-0.2
|
|
1
|
至軽風
|
light air
|
風向きは煙がなびくのでわかるが、風見には感じない。
|
鱗のようなさざ波ができるが、波頭に泡はない。
|
1-3
|
0.3-1.5
|
|
2
|
軽風
|
light breeze
|
顔に風を感じる。木の葉が動く。風見も動きだす。
|
小波の小さいもので、まだ短いがはっきりしてくる。波頭は滑らかに見え、砕けていない。
|
4-6
|
1.6-3.3
|
|
3
|
軟風
|
gentle breeze
|
木の葉や細かい小枝がたえず動く。軽く旗が開く。
|
小波の大きいものは波頭が砕けはじめる。泡はガラスのように見える。所々に白波が現れることがある。何種類かのディンギーはプレーニングはじめる。
|
7-10
|
3.4-5.4
|
|
4
|
和風
|
moderate breeze
|
砂埃がたち、紙片が舞い上がる。小枝が動く。
|
波の小さいもので長くなる。白波がかなり多くなる。多くの種類のディンギーはプレーニングできる。
|
11-16
|
5.5-7.9
|
|
5
|
疾風
|
fresh breeze
|
葉のある灌木がゆれはじめる。池や沼の水面に波頭がたつ。
|
波の中位のもので、一層はっきりして長くなる。白波がたくさんあらわれる。(しぶきを生じることもある)
|
17-21
|
8.0-10.7
|
|
6
|
雄風
|
strong breeze
|
大枝が動く。電線が鳴る。傘はさしにくい。
|
波の大きいものができはじめる。いたる所で白く泡立った波頭の範囲が一層広くなる。(しぶきを生じることが多い)
どのディンギーも上りのコースで、突風のきたときに、シートをゆるめなければならない。
|
22-27
|
10.8-13.8
|
|
7
|
強風
|
near gale
|
樹木全体がゆれる。風に向かっては歩きにくい。
|
波はますます大きくなり、波頭が砕けてできた白い泡は、筋を引いて風下に
吹き流されはじめる。
|
28-33
|
13.9-17.1
|
|
8
|
疾強風
|
gale
|
小枝が折れる。風に向かっては歩けない。
|
大波のやや小さいもので、長さが長くなる。波頭の端は砕けて水煙となりはじめる。泡は明瞭な筋を引いて風下に吹き流される。ほとんどのディンギー帆走不能。
|
34-40
|
17.2-20.7
|
|
9
|
大強風
|
strong gale
|
人家にわずかの損害がおこる。煙突が倒れ、瓦がはがれる。
|
大波。泡は濃い筋を引いて風下に吹き流される。波頭はのめり崩れ落ち、逆巻きはじめる。しぶきのために視程が損なわれることもある。
|
41-47
|
20.8-24.4
|
|
10
|
全強風
|
storm
|
陸地の内部ではめずらしい。樹木が根こそぎになる。人家に大損害がおこる。
|
波頭が長くのしかかるような非常に高い大波。大きな塊となった泡は濃い白色の筋を引いて、風下に吹き流される。海面は全体として白く見える。海面は長い白色の泡の塊で完全に覆われる。波の崩れ方は激しく、衝撃的となる。波頭は吹き飛ばされて水煙となり視界も損なわれる.
|
48-55
|
24.5-28.4
|
|
11
|
暴風
|
violent storm
|
めったに起こらない広い範囲の破壊を伴う。
|
山のように高い大波。(中小船舶は波の陰に見えなくなることもある)海面は風下に吹き流された長い白色の泡の塊で完全に覆われる。いたる所で波頭の端が吹き飛ばされて水煙となる。視程は損なわれる。大気は泡としぶきで充満する。
|
56-63
|
28.5-32.7
|
|
12
|
颱風
|
hurricane
|
-
|
-
|
>63
|
>32.8
|
風の強さと吹き方
| 平均風速[m/s]
| おおよその時速[km/h]
| 風 圧 [kgf/m2] |
予報用語 |
速さの目安 |
人への影響 |
屋外・樹木の様子
| 車に乗っていて |
建造物の被害 |
| 10~15 |
~50 |
~11.3 |
やや強い風 |
一般道路の自動車 |
風に向って歩きにくくなる。傘がさせない。 |
樹木全体が揺れる。電線が鳴る |
道路の吹流しの角度、水平(10m/s),高速道路で乗用車が横風に流される感覚を受ける |
取り付けの不完全な看板やトタン板が飛び始める |
| 15~20 |
~70 |
~20.0 |
強い風 |
高速道路の自動車 |
風に向って歩けない。転倒する人もでる。 |
小枝が折れる |
高速道路では、横風に流される感覚が大きくなり、通常の速度で運転するのが困難となる |
ビニールハウスが壊れ始める |
| 20~25 |
~90 |
~31.3 |
非常に強い風 |
しっかりと身体を確保しないと転倒する。 |
車の運転を続けるのは危険な状態となる |
鋼製シャッターが壊れ始める。風で飛ばされた物で窓ガラスが割れる |
| 25~30 |
~110 |
~45.0 |
立っていられない。屋外での行動は危険。 |
樹木が根こそぎ倒れはじめる |
ブロック塀が壊れ、取り付けの不完全な屋外外装材がはがれ、飛び始める |
| 30~ |
110~ |
45.0~ |
猛烈な風 |
特急列車 |
屋根が飛ばされたり、木造住宅の全壊が始まる |
★コスモス
--------------------------------------------------------------------------------------------
 市の花「コスモス」は、茂原市制施行四十五周年を記念して、市民の方々からの公募提案をもとに、平成9年10月20日に選定されました。
市の花「コスモス」は、茂原市制施行四十五周年を記念して、市民の方々からの公募提案をもとに、平成9年10月20日に選定されました。
メキシコ高原原産といわれても信じられない程身近な花ですが、コロンブスのアメリカ大陸発見後、ヨーロッパに渡り(18世紀末にスペインマドリードの植物園に送られる)改良された後、わが国に渡来(日本には明治20年頃に渡来したと言われる)。
原産地にコスモス属が多種あるなかから、花色が紅、ピンク、白の「コスモス」と黄色系で形態も違う「黄花コスモス」の2種が園芸種の基礎に。
近頃見かける黄色い花のコスモスは、「黄花コスモス」と異なり、ピンクに黄色の条(すじ)がある品種から日本で改良されたものです。
コスモスの語源はギリシャ語で「秩序」の意とか、整然とした花弁からの命名のようです。和名では秋桜、さだまさしの歌の題名にもなっていますが、
植物分類ではキク科に属し、サクラの仲間ではありません。基本的には短日で花芽を分化する性質から花の季節は秋。しかし昨今は園芸での改良が進み、
周年で咲くものもあります。通常は草丈が1~2mのところ、もっと短いものもあります。
市内には休耕田いっぱいにコスモスを咲かせているところがあちこちにあります。
因みに花言葉は、「乙女の真心」でコスモスのやさしい様子を伝えています。でもコスモスは見かけよりも芯の強い植物です。
ところで、葉数はいくつ?
そんなこと聞かれても、コスモスの葉数!あんなに細かな葉なんて。でも意外と分り易く、茎からでている葉の付け根を数えればよいのです。
茎からでた部分が一つの葉に相当、それがスジ状に細かく分かれた形なのです。
原産地メキシコ高原は、乾燥した強い風にさらされた土地。そんな環境に適するように、気孔を少なくして乾燥に耐え、風邪で倒れないような形状になったとのことです。
花占いのご注意
写生で正しく花を描いていますか、花びらを8枚!
「好き、嫌い…」と花びらを取りながらの恋占いでは、「嫌い」から始めないと、「好き」で終わりになりません。
花のおしべ、めしべはどこ?実は中心部の黄色いツブツブが花(筒状花)で、見えにくいけれど5つの花びら、おしべ、めしべを備える100個程の花の集まりです。
周囲の花びらは筒状花が進化してできた舌状花で、花粉を運んでもらうハチをひきつける役割があり、ハチから見えやすいように、紫外線でよく見える色になっているのだそうです。
舌状花先端のギザギザが、筒状花から進化したなごりなのです
★パニック発作チェック表
--------------------------------------------------------------------------------------------
 次の症状が四つ以上ありましたか?
次の症状が四つ以上ありましたか?
①動悸、心拍数の増加
②発汗
③身震い、震え
④息切れ感、息苦しさ
⑤窒息感
⑥胸痛、胸の不快感
⑦吐き気、腹部の不快感
⑧めまい、ふらつき、頭が軽くなる、気が遠くなる
⑨現実でない感じ、離人症状(自分自身から離れている)
⑩コントロールを失うこと、気が狂うことへの恐怖
⑪死への恐怖
⑫感覚まひ、うずき
⑬冷感、熱感
「DSM-IV-TR 精神疾患の分類と診断の手引」(医学書院)から
★鬼のいわれ
--------------------------------------------------------------------------------------------
 「隠れる」という意味の「オン(隠)」という言葉から変化して「オニ」になったといわれている。
「隠れる」という意味の「オン(隠)」という言葉から変化して「オニ」になったといわれている。
鬼はどうして角と寅のパンツをはいているのか?
牛の角頭に虎皮の腰蓑という鬼の姿は、陰陽道の鬼が集まる鬼門(きもん)が、
北東(艮=うしとら:丑と寅の間)の方位であることから影響を受けている。
★観光・文化・教育
--------------------------------------------------------------------------------------------

★土用の丑の日
--------------------------------------------------------------------------------------------
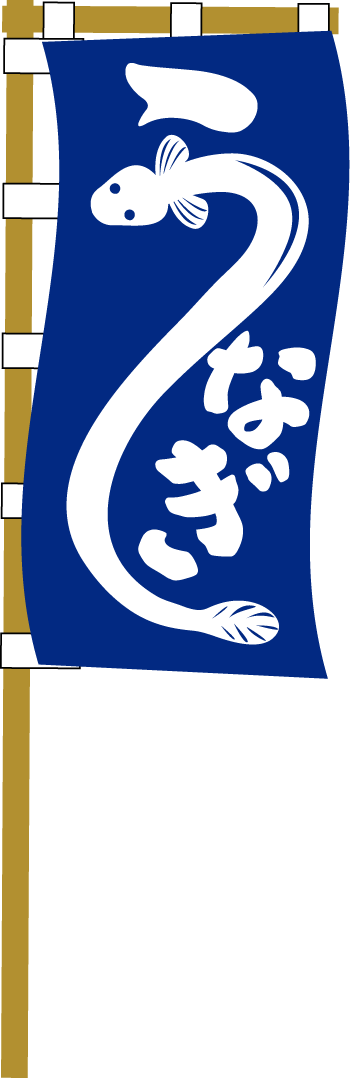 土用の丑の日とは
土用の丑の日とは
土用とは、
元々土旺用事と言ったものが省略されたもの。
昔々、世の中の全てが木火土金水の五つの組み合わせで成り立つという五行説を季節にも割り振ることを考えた人が居たみたいですが、昔も今も季節は「四季」で「五季」とはいいませんから、
木-春
火-夏
金-秋
水-冬
土-???
と割り振ったら「土」が余ってしまった。そこで、
「土の性質は全ての季節に均等に存在するだ!」とこじつけて、各季節の最後の18~19日を「土用」としました。
(これで1年の日数が均等に五行に割り振られたことになります)。
丑の日は、
丑の日の「丑」は十二支の「子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥」の丑です。
各土用の中で丑の日にあたる日が「土用丑の日」、一般的には「夏土用の最初の丑の日」に鰻屋の祭り「土用丑」と称して鰻を食べる日ということになっています。
2回目の「土用丑」は皆疲れているのか、飽きるのか、あまり盛り上がらない。
土用丑の日とウナギ
夏の土用の時期は暑さが厳しく夏ばてをしやすい時期ですから、昔から「精の付くもの」を食べる習慣があり、土用蜆(しじみ)、土用餅、土用卵などの言葉が今も残っています。
また精の付くものとしては「ウナギ」も奈良時代頃から有名だったようで、土用ウナギという風に結びついたのでしょう。
今のように土用にウナギを食べる習慣が一般化したきっかけは幕末の万能学者として有名な平賀源内が、
夏場にウナギが売れないので何とかしたいと近所のウナギ屋に相談され、
「本日、土用丑の日」
と書いた張り紙を張り出したところ、大繁盛したことがきっかけだと言われています。
丑とうなぎの「う」がいっしょだから??
この時、平賀源内が焼き鳥屋さんに相談を受けていたとしたら今ごろは・・・・・・。
なぜ丑の日なのか? ウナギなのか?
丑の日とウナギの関係ですが、丑の日の「う」からこの日に「うのつくもの」を食べると病気にならないと言う迷信もあり、「ウナギ」もこれに合致した食べものであった!?
別の説では、十二支のうち「丑辰未戌」の4つが五行説の「土」に配当されています。
ひょとすると「土用最初の土の日」・・・・・かも知れません。
★皆既日食2009/07/22
--------------------------------------------------------------------------------------------
 東京
欠け始め: 09:53
食最大: 11:08 (食分0.75)
食終了: 12:28
東京
欠け始め: 09:53
食最大: 11:08 (食分0.75)
食終了: 12:28
日本では、全国で部分日食を観察することができます。また奄美大島北部、トカラ列島、屋久島、種子島南部など、皆既日食帯と呼ばれる細長くのびた地域・海域内では、皆既日食を観察することができます。
皆既日食になると、太陽のまわりにはコロナが広がって見られます。また太陽表面から吹き出ている赤いプロミネンスなども観察することができます。空は、程度は日食ごとに違いますが、夕方・明け方の薄明中のように暗くなり、明るい星ならば見ることができます。地平線近くは、夕焼け(朝焼け)のように空が赤く染まって見られます。
日本の陸地に限ると、皆既日食が観察できるのは1963年7月21日の北海道東部で見られた皆既日食以来、実に46年ぶりです。次回も2035年9月2日の北陸・北関東などで見られる皆既日食まで26年間起こりません。非常に珍しい現象と言えるでしょう。
本州 (2009/07/22部分日食)
東京~大阪の地域でも太陽は7割以上も欠けます。
普段見る青空は不気味な薄暗い色になり、真夏のギラギラした太陽は弱々しい光になり、誰もが太陽の異変に気付くことでしょう。真夏の真昼間の眩しいはずの日なたは、まるで日没直前の夕日が差しているような感じになるでしょう。関東~九州で太陽がこれほど深く欠けた日食は過去20年間に一度もありませんでしたので、何も知らない人は突然の「天変」にきっと驚かされることでしょう。
★落し物と税金
--------------------------------------------------------------------------------------------

落とし主が現れない場合は?
遺失物法に定めがあり、落とし主が分からない、または取りに来なかった場合は、警察に届け出てから3ヶ月後に拾い主のものになります。以前は6ヶ月だったこの期間が平成19年の改正により、3ヶ月に短縮されています。
ただし、拾い主が引き取ることができる期間は、権利が発生(警察に届け出てから3ヶ月後)してから、2ヶ月以内になります。この落し物の2ヶ月の引き取り期間については、警察から改めて通知はありませんので、「拾得物件預り書」や「お知らせハガキ」を大切に保管しておくことが必要です。
謝礼の相場は?
遺失物法に定めがあり、拾い主に対して拾った物の価値の5%~20%の謝礼(報労金)を支払わなければならない、とされています。
拾得物や謝礼の税金は?
一時所得として課税の対象になります。
一時所得は、(収入-50万円)×1/2が所得となり、税金がかかります。従って、150万円拾得で仮に落とし主が現れなかった場合には、(150万円-50万円)×1/2=50万円が拾い主の所得になり、税金の対象になります。
なお、一時所得は収入から50万円を差し引きますので、拾った金額(もしくは謝礼)が50万円以下で、その年に他の一時所得がなければ結果的に税金はかからないことになります。
★貨 幣 豆 知 識
--------------------------------------------------------------------------------------------


★脳卒中予防のお酒について
--------------------------------------------------------------------------------------------

日本酒1合は、よく聞きますが、最近は、ビールや焼酎・ワインなど、いろいろ飲まれる方が増えてます。
そこで、お酒の適量(以下のうちいずれか)をまとめてみました。
1.日本酒
1合(180ml)
2.ウイスキー・ブランデー
ダブル1杯(60ml)
3.焼酎
ぐい飲み1杯(70ml)
4.ビール
中ビン1本/ロング缶1本(500ml)
5.ワイン
グラス1.5~2杯(200ml)
ざっと、次のようにも言えます。
日本酒3合=ビール大びん3本=ウイスキーダブル3杯=焼酎2合=グラスワイン6杯
1升(しょう)=10合(ごう)=1.8リットル
★頭を強く打ったあとは
--------------------------------------------------------------------------------------------

頭を強く打った時には、脳にいろいろな変化がおきます。特に頭蓋骨の内側に出血が起こると、生命に危険を及ぼすこともあります。
これらの症状は、頭を打った後すぐに出る場合から、少し時間がたってからでることもあります。
今のところ症状がなく、医師の診断でも特に異常がないとしても、全く大丈夫とは言い切れません。次のような症状が現れたら、出来る限り早く医療機関に受診して下さい。痙攣をおこしたり、意識が悪くなったりしたら、救急車をお願いしても良いでしょう。夜間寝ている時も二、三回起こし寝ているか意識がないか確認してく下さい。
1. 吐き気があって、嘔吐を繰り返す。
2. ぼんやりしたり、ほっておくとすぐに寝てしまったり、起こしてもなかなか起きない。
3. 手足が動きにくかったり、しびれたりする。
4. 痙攣が起きる。
5. 頭痛が強くて、痛み止めでもなかなか良くならない。
6. 物が見えづらくなったり、物が二重に見えたりする。
7. めまいや、ふらつきが強く、まっすぐに歩きづらくなる。
なお、特に症状を訴えられない乳幼児の場合は、症状がわかりにくく、急に症状が出る場合があります。頭を強く打った後、入浴は避け、1~2日は安静に保ち、決して一人にはしないようにしましょう。
上記の症状などが認められた場合は、出来るだけ早めに電話連絡したのち医師の診察を受けてください
★同窓会案内状の返信の仕方
--------------------------------------------------------------------------------------------
 案内状や招待状をいただいたときの返信の仕方です。
案内状や招待状をいただいたときの返信の仕方です。
往復はがきは同封のはがきに返信する場合
1 ご出席
ご欠席
と、書いてあると思います。
出席か欠席かをまず伝えます。
「ご」を2重線で消してください。
つい、丸をつけたくなりますが、丸をつけないようにしてくださいね。
そして、出席・欠席の後に「させていただきます」と書き添えると丁寧です。
あと、表のほうを見てください。
宛名の下に「行」とあると思います。
この「行」を同様に2重線で消して「様」に訂正しておいてください。
2 出席の場合
近況報告や同窓会(クラス会)を楽しみにしていることを伝えます。
欠席の場合
理由を簡潔に書きます。この場合も、近況も書いておくと当日会場で欠席者の近況を報告する場合もあるので簡潔に。
特に理由がない場合は、「仕事が忙しく・・・」「体調が優れないので・・・」などと、無難な理由がよいと思います。
「まことに残念ながら」や「大変心苦しいのですが」などと付け加えるとお断りの言葉が柔らかくなりますね。
3 スペースに余裕があれば、幹事や主催者にお礼の言葉を添えるといいと思います。
4 ご住所
ご芳名
最後に住所と名前ですが、ここも「ご」「ご芳」も2重線で消してお書きください。
指定期日が書いてあると思いますので、お早めにお返事を出してください。
★昔の時間の表現
--------------------------------------------------------------------------------------------
 午前0時を子(前後1時間)
午前0時を子(前後1時間)
2時間ごとに下記のように
子 午後11時~午前 1時
丑 午前 1時~午前 3時
寅 午前 3時~午前 5時
卯 午前 5時~午前 7時
辰 午前 7時~午前 9時
巳 午前 9時~午前11時
午 午前11時~午後 1時
未 午後 1時~午後 3時
申 午後 3時~午後 5時
酉 午後 5時~午後 7時
戌 午後 7時~午後 9時
亥 午後 9時~午後11時
簡単な方法は数えて1を引き2倍する
子3刻 9つ 0:00 辰3刻 5つ 8:00 申3刻 7つ 16:00
丑初刻 9つ半 1:00 巳初刻 5つ半 9:00 酉初刻 7つ半 17:00
丑3刻 8つ 2:00 巳3刻 4つ 10:00 酉3刻 6つ 18:00
寅初刻 8つ半 3:00 午初刻 4つ半 11:00 戌初刻 6つ半 19:00
寅3刻 7つ 4:00 午3刻 9つ 12:00 戌3刻 5つ 20:00
卯初刻 7つ半 5:00 未初刻 9つ半 13:00 亥初刻 5つ半 21:00
卯3刻 6つ 6:00 未3刻 8つ 14:00 亥3刻 4つ 22:00
辰初刻 6つ半 7:00 申初刻 8つ半 15:00 子初刻 4つ半 23:00
丑初刻 1:00
丑初刻1分 1:03
丑初刻2分 1:06
・・・・・・・・・
丑初刻9分 1:27
丑2刻 1:30
丑2刻1分 1:33
・・・・・・・・・
丑4刻9分 2:57
寅初刻 3:00
★干支
--------------------------------------------------------------------------------------------
 干支(えと=十干十二支:じゅっかんじゅうにし)
干支(えと=十干十二支:じゅっかんじゅうにし)
十干
十干とは「甲(こう)・乙(おつ)・丙(へい)・丁(てい)・戊(ぼ)・己(き)・庚(こう)・辛(しん)・壬(じん)・葵(き)」の総称である。
もともと十干は,日の順序を示すための符号であったようだ。
中国の殷の時代(紀元前14~15世紀)に十日を一旬として占う卜順(ぼくじゅん)が行われており、この十日ごとに循環する日を表示する数詞として用いられたのが起源と云われる。
これが後に陰陽五行説、十二支と結びついて複雑な読みと意味を持つようになった。
十干に陰陽と五行とを配置。
| 十干 | 読み | 二行 | 五行 | 読み | |
|---|
| 甲 | こう | 陽 | 木 | 木の兄(きのえ) | |
| 乙 | おつ | 陰 | 木 | 木の弟(きのと) | |
| 丙 | へい | 陽 | 火 | 火の兄(ひのえ) | |
| 丁 | てい | 陰 | 火 | 火の弟(ひのと) | |
| 戊 | ぼ | 陽 | 土 | 土の兄(つちのえ) | |
| 己 | き | 陰 | 土 | 土の弟(つちのと) | |
| 庚 | こう | 陽 | 金 | 金の兄(かねのえ) | |
| 辛 | しん | 陰 | 金 | 金の弟(かねのと) | |
| 壬 | じん | 陽 | 水 | 水の兄(みずのえ) | |
| 葵 | き | 陰 | 水 | 水の弟(みずのと) | |
陽を兄(え)、陰を弟(と)する。
陽の兄の性格は剛強・動であり、陰の弟の性格は柔和・静であるとされる。 |
十二支
十二支とは「子(し)・丑(ちゅう)・寅(いん)・卯(ぼう)・辰(しん)・巳(し)・午(ご)・未(び)・申(しん)・酉(ゆう)・戌(じゅつ)・亥(がい)」の総称である。
十二支はもともと十二ヶ月の順序を表示する符合であり、中国の殷の時代には使われていたという。
その後、子・丑・・では覚え難いのでそれぞれに動物を割り当てて呼ぶようになった。これを十二支獣(じゅうにしじゅう)という。
「子(ね)・丑(うし)・寅(とら)・卯(う)・辰(たつ)・巳(み)・午(うま)・未(ひつじ)・申(さる)・酉(とり)・戌(いぬ)・亥(い)」の読みはこの十二支獣を起因としている。
十二支は月のほか時刻、方位を配置されている。
| 十二支 | 読 み | 獣 | 月 | 時 刻 | 方 位 |
|---|
| 子 | し | ね | 鼠 | 11月 | 0時 | 北 |
| 丑 | ちゅう | うし | 牛 | 12月 | 2時 | 北北東 |
| 寅 | いん | とら | 虎 | 1月 | 4時 | 東北東 |
| 卯 | ぼう | う | 兎 | 2月 | 6時 | 東 |
| 辰 | しん | たつ | 竜 | 3月 | 8時 | 東南東 |
| 巳 | し | み | 蛇 | 4月 | 10時 | 南南東 |
| 午 | ご | うま | 馬 | 5月 | 12時 | 南 |
| 未 | び | ひつじ | 羊 | 6月 | 14時 | 南南西 |
| 申 | しん | さる | 猿 | 7月 | 16時 | 西南西 |
| 酉 | ゆう | とり | 鶏 | 8月 | 18時 | 西 |
| 戌 | じゅつ | いぬ | 犬 | 9月 | 20時 | 西北西 |
| 亥 | がい | い | 猪 | 10月 | 22時 | 北北西 |
干支(十干十二支)
十干と十二支をを組合せ、その最小公倍数の60の周期で日、年を数えるのに用いられた。
これを「干支」「十干十二支」「六十干支」「えと」「甲子(かっし)」と呼ばれるものである。
日本の歴史には六十年以上用いられてきた元号は昭和以外にないので、たとえば、天平乙酉といえば天平十七年(745年)のことである。
また、戦乱などをその年の干支で名付けるられている。その例としては「壬申の乱(672)」「戊辰戦争(1868)」などがある。
ちなみに昭和元年は「丙寅」であり、昭和61年・62年・63年はそれぞれ「丙寅」「丁卯」「戊辰」と昭和の元号のなかで二度目の干支を迎えた。
| 十干 | 五行 | 十二支 | 六十干支 | 読み | 備考 |
|---|
| 1 | 甲 | 木の兄 | 子 | 甲子 | きのえね | かっし | |
| 2 | 乙 | 木の弟 | 丑 | 乙丑 | きのとうし | いっちゅう | |
| 3 | 丙 | 火の兄 | 寅 | 丙寅 | ひのえとら | へいいん | |
| 4 | 丁 | 火の弟 | 卯 | 丁卯 | ひのとう | ていぼう | |
| 5 | 戊 | 土の兄 | 辰 | 戊辰 | つちのえたつ | ぼしん | |
| 6 | 己 | 土の弟 | 巳 | 己巳 | つちのとみ | きし | |
| 7 | 庚 | 金の兄 | 午 | 庚午 | かのえうま | こうご | |
| 8 | 辛 | 金の弟 | 未 | 辛未 | かのとひつじ | しんび | |
| 9 | 壬甲 | 水の兄 | 申 | 壬申 | みずのえさる | じんしん | |
| 10 | 葵 | 水の弟 | 酉 | 癸酉 | みずのととり | きゆう | |
| 11 | 甲 | 木の兄 | 戌 | 甲戌 | きのえいぬ | こうじゅつ | |
| 12 | 乙 | 木の弟 | 亥 | 乙亥 | きのとい | いつがい | |
| 13 | 丙 | 火の兄 | 子 | 丙子 | ひのえね | へいし | |
| 14 | 丁 | 火の弟 | 丑 | 丁丑 | ひのとうし | ていちゅう | |
| 15 | 戊 | 土の兄 | 寅 | 戊寅 | つちのえとら | ぼいん | |
| 16 | 己 | 土の弟 | 卯 | 己卯 | かっし | つちのとう | |
| 17 | 庚 | 金の兄 | 辰 | 庚辰 | かのえたつ | こうしん | |
| 18 | 辛 | 金の弟 | 巳 | 辛巳 | かのとみ | しんし | |
| 19 | 壬 | 水の兄 | 午 | 壬午 | みずのえうま | じんご | |
| 20 | 葵 | 水の弟 | 未 | 癸未 | みずのとひつじ | きび | |
| 21 | 甲 | 木の兄 | 申 | 甲申 | きのえさる | こうしん | |
| 22 | 乙 | 木の弟 | 酉 | 乙酉 | きのととり | いつゆう | |
| 23 | 丙 | 火の兄 | 戌 | 丙戌 | ひのえいぬ | へいじゅつ | |
| 24 | 丁 | 火の弟 | 亥 | 丁亥 | ひのとい | ていがい | |
| 25 | 戊 | 土の兄 | 子 | 戊子 | つちのえね | ぼし | |
| 26 | 己 | 土の弟 | 丑 | 己丑 | つちのとうし | きちゅう | |
| 27 | 庚 | 金の兄 | 寅 | 庚寅 | かのえとら | こういん | |
| 28 | 辛 | 金の弟 | 卯 | 辛卯 | かのとう | しんぼう | |
| 29 | 壬 | 水の兄 | 辰 | 壬辰 | みずのえたつ | じんしん | |
| 30 | 葵 | 水の弟 | 巳 | 癸巳 | みずのとみ | きし | |
| 31 | 甲 | 木の兄 | 午 | 甲午 | きのえうま | こうご | |
| 32 | 乙 | 木の弟 | 未 | 乙未 | きのとひつじ | いつび | |
| 33 | 丙 | 火の兄 | 申 | 丙申 | ひのえさる | へいしん | |
| 34 | 丁 | 火の弟 | 酉 | 丁酉 | ひのととり | ていゆう | |
| 35 | 戊 | 土の兄 | 戌 | 戊戌 | つちのえいぬ | ぼじゅつ | |
| 36 | 己 | 土の弟 | 亥 | 己亥 | つちのとい | きがい | |
| 37 | 庚 | 金の兄 | 子 | 庚子 | かのえね | こうし | |
| 38 | 辛 | 金の弟 | 丑 | 辛丑 | かのとうし | しんちゅう | |
| 39 | 壬 | 水の兄 | 寅 | 壬寅 | みずのえとら | じんいん | |
| 40 | 葵 | 水の弟 | 卯 | 癸卯 | みずのとう | きぼう | |
| 41 | 甲 | 木の兄 | 辰 | 甲辰 | きのえたつ | こうしん | |
| 42 | 乙 | 木の弟 | 巳 | 乙巳 | きのとみ | いつし | |
| 43 | 丙 | 火の兄 | 午 | 丙午 | ひのえうま | へいご | |
| 44 | 丁 | 火の弟 | 未 | 丁未 | ひのとひつじ | ていび | |
| 45 | 戊 | 土の兄 | 申 | 戊申 | つちのえさる | ぼしん | |
| 46 | 己 | 土の弟 | 酉 | 己酉 | つちのととり | きゆう | |
| 47 | 庚 | 金の兄 | 戌 | 庚戌 | かのえいぬ | こうじゅつ | |
| 48 | 辛 | 金の弟 | 亥 | 辛亥 | かのとい | じんがい | |
| 49 | 壬 | 水の兄 | 子 | 壬子 | みずのえね | じんし | |
| 50 | 葵 | 水の弟 | 丑 | 癸丑 | みずのとうし | きちゅう | |
| 51 | 甲 | 木の兄 | 寅 | 甲寅 | きのえとら | こういん | |
| 52 | 乙 | 木の弟 | 卯 | 乙卯 | きのとう | いつぼう | |
| 53 | 丙 | 火の兄 | 辰 | 丙辰 | ひのえたつ | きへいしん | |
| 54 | 丁 | 火の弟 | 巳 | 丁巳 | ひのとみ | ていし | |
| 55 | 戊 | 土の兄 | 午 | 戊午 | つちのえうま | ぼご | |
| 56 | 己 | 土の弟 | 未 | 己未 | つちのと | きび | |
| 57 | 庚 | 金の兄 | 申 | 庚申 | かのえさる | こうしん | |
| 58 | 辛 | 金の弟 | 酉 | 辛酉 | かのととり | しんゆう | |
| 59 | 壬 | 水の兄 | 戌 | 壬戌 | みずのえいぬ | じんじゅつ | |
| 60 | 葵 | 水の弟 | 亥 | 癸亥 | みずのとい | きがい | |
★明るさの目安(自転車のライト)
--------------------------------------------------------------------------------------------

A.認識灯レベル 20 lm前後。砲弾型LED数個ぐらいの明るさ。無灯火でも走れるほど明るい道で使う。
B.ハブダイナモレベル 35 lm前後。LED0.5Wやフィラメント球2.4Wの明るさ。薄暗い道でも走れる。
C.猫目(CatEye)レベル 45 lm前後。LED1W、EL510、EL520クラスの明るさ。薄暗い道でも走れる。
D.懐中電灯(低)レベル 60 lm前後。ホムセンで買える懐中電灯の明るさ。薄暗い道でも走れる。
E.ドサンレベル 100 lm前後。ドサンM1、SG-305、EL610、EL710クラスの明るさ。かなり暗い道でも走れる。
F.懐中電灯(中)レベル 200 lm前後。L2Dなど最新LED3WクラスやEL700の明るさ。かなり暗い道でも走れる。
G.懐中電灯(高)レベル 300 lm前後。Cree多灯、MC-E、SSCP7、ムーンシャイン3Hの明るさ。真っ暗な道でも走れる。
H.HID10Wレベル 500 lm前後。ムーンシャインHIDクラスの明るさ。真っ暗な道でも走れる。
I.原付レベル 1000 lm前後。新車の原付ライト並みの明るさ。真っ暗な道でも走れる。
J.自動車レベル 2000 lm以上。自動車(2800lm)並みの明るさ。真っ暗な道でも安心して走れる。
注1 lm=ルーメンは光源の明るさの単位。集光度合で変化するスポットの明るさとは意味合いが違うので注意。
注2 走れるかどうかの基準は、日中と同じペースで楽に走れるかどうか。
★家紋の武将豆知識
--------------------------------------------------------------------------------------------


★国際電話・国コード表
--------------------------------------------------------------------------------------------

地域別/五十音順
|
国名(日本語) |
国名(英語) |
国コード |
| 日本 |
Japan |
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
★Fスケール(竜巻の強さ)
--------------------------------------------------------------------------------------------

竜巻などの激しい突風をもたらす現象は水平規模が小さく、既存の風速計から風速の実測値を得ることは困難です。このため、1971年にシカゴ大学の藤田哲也博士により、竜巻やダウンバーストなどの突風により発生した被害の状況から風速を大まかに推定する藤田スケール(Fスケール)が考案されました。
被害が大きいほどFの値が大きく、風速が大きかったことを示します。日本ではこれまでF4以上の竜巻は観測されていません。
| F0 | 17~32m/s
(約15秒間の平均) | テレビのアンテナなどの弱い構造物が倒れる。小枝が折れ、根の浅い木が傾くことがある。非住家が壊れるかもしれない。 |
| F1 | 33~49m/s
(約10秒間の平均) | 屋根瓦が飛び、ガラス窓が割れる。ビニールハウスの被害甚大。根の弱い木は倒れ、強い木は幹が折れたりする。走っている自動車が横風を受けると、道から吹き落とされる。 |
| F2 | 50~69m/s
(約7秒間の平均) | 住家の屋根がはぎとられ、弱い非住家は倒壊する。大木が倒れたり、ねじ切られる。自動車が道から吹き飛ばされ、汽車が脱線することがある。 |
| F3 | 70~92m/s
(約5秒間の平均) | 壁が押し倒され住家が倒壊する。非住家はバラバラになって飛散し、鉄骨づくりでもつぶれる。汽車は転覆し、自動車はもち上げられて飛ばされる。森林の大木でも、大半折れるか倒れるかし、引き抜かれることもある。 |
| F4 | 93~116m/s
(約4秒間の平均) | 住家がバラバラになって辺りに飛散し、弱い非住家は跡形なく吹き飛ばされてしまう。鉄骨づくりでもペシャンコ。列車が吹き飛ばされ、自動車は何十メートルも空中飛行する。1トン以上ある物体が降ってきて、危険この上もない。 |
| F5 | 117~142m/s
(約3秒間の平均) | 住家は跡形もなく吹き飛ばされるし、立木の皮がはぎとられてしまったりする。自動車、列車などがもち上げられて飛行し、とんでもないところまで飛ばされる。数トンもある物体がどこからともなく降ってくる。 |
★お 盆 関 連
--------------------------------------------------------------------------------------------
 お盆についてのいろいろです。
お盆についてのいろいろです。
●迎え火・送り火
13日の夕方に家の前で、焙烙(ほうろく)という素焼きの皿の上でおがらを焚いて、ご先祖や故人の霊をお迎えする「精霊(しょうりょう)迎え」をします。その霊が迷わず帰って来る目印にするのが「迎え火」です。精霊(しょうりょう)とは亡くなった人々の霊のことです。
お盆提灯には迎え火、送り火の役割がありますので、実際に火を焚くのが難しいご家庭では、お盆提灯を飾って迎え火とします。
お墓参りをして、墓地で盆提灯に明かりを灯し、その提灯を持って帰り、霊を自宅まで導くという風習の地域もあります。
お盆の間一緒に過ごしたご先祖の霊を送り帰す「精霊(しょうりょう)送り」のために、16日に再び、焙烙でおがらを焚くのが「送り火」です。
京都の有名な大文字焼きも、送り火のひとつです。
焙烙(ほうろく)は仏壇屋で、おがらはスーパーや花屋で求めることが出来ます。
おがらは、麻の皮をはいだ後の茎を乾燥させたものです。
浄土真宗では、迎え火で霊をお迎えする習わしはありませんが、お盆の間はお盆提灯を飾って仏さまとご先祖に報恩感謝をささげます。
●精霊棚(盆棚)
多くの地方では12日か13日の朝に、ご先祖や故人の霊を迎えるための精霊棚(しょうりょうだな)(盆棚)をつくります。
台の上に真菰(まこも)の筵(むしろ)を敷き、位牌を中心に安置し、仏具、お花、ナスやキュウリ、季節の野菜や果物、精進料理を供えた仏膳(霊供膳)などを供えます。
蓮の葉にナスやキュウリをさいの目に刻んで洗い米と一緒に入れた「水の子」、蓮の葉に水をたらした「閼伽水(あかみず)」、みそはぎ、ほおずき、などを供える場合もあります。
精霊棚(盆棚)のつくり方は地域によって異なりますが、精霊棚(盆棚)を設けるのが難しい場合は、仏壇の前に小さな机を置いてお供え物を置きます。
真菰などのお盆用品は、スーパーで求めることが出来ます。
●お盆の習わし
最近では、特に都市部において、住宅事情などから精霊棚(盆棚)を設けずに、お仏壇にお供えをするやり方も増えています。
一般的には、盆提灯を飾り、お花やお供え物を普段より多めにし、精進料理を供えた仏膳(霊供膳)などを供えます。
お盆の習わしは、地域や宗派によって、あるいは時代によって、さまざまに形を変えながら伝えられてきました。
その意味では、これが絶対に正しいやり方という決まりはありませんが、詳しくは菩提寺のご住職にお聞きになるとよいでしょう。
地域によってはこの時期に、菩提寺のご住職が檀家を回ってお経をあげる、棚経(たなきょう)も行われます。
何よりもお盆で大切なことは、家族や親戚が集まり、ご先祖や故人を偲び、今日ある自分をかえりみて、感謝供養することではないでしょうか。
●新盆
故人が亡くなって四十九日の後、初めて迎えるお盆を新盆といい、「にいぼん・しんぼん・はつぼん」などと呼びます。
四十九日の忌明けより前にお盆を迎えた時は、その年でなく、翌年のお盆が新盆となります。
新盆は故人の霊が初めて帰って来るという考えから、自宅で、家族や親戚のほか、故人と親しかった方々を招いて、普段のお盆より特に丁寧に供養を営みます。菩提寺のご住職に来ていただき、お経をあげてもらう場合も多いです。
また新盆は、知人が突然おまいりに来ることもあるので、その準備も考えておきます。
新盆には、普通の絵柄の入った盆提灯のほかに、白い新盆用の提灯を飾ります。この白提灯を飾るのは新盆の時だけで、お盆が終わったら燃やして処分します。(燃やして処分ができない場合は、「お盆が終わった盆提灯」を参照)
●盆提灯
お盆には、ご先祖や故人の霊が迷わず帰って来る目印として、盆提灯を飾るのが習わしになっています。
また盆提灯は、その家の中に霊が滞在しているしるしであるとされ、鎌倉時代からこの盆提灯の習慣は行われていました。
最近では新盆には、親戚や故人と親しかった方々は、故人の供養のためにお供え物をしますが、盆提灯はお供えとして最高のものとされています。
むかしは、新盆用の白提灯は故人のご家族が購入し、普通の絵柄の入った盆提灯は、兄弟、親戚などから贈られていました。
しかし最近では、盆提灯を飾るスペースなどの住宅事情を考えて、兄弟、親戚などから盆提灯用にと現金で頂戴して、故人のご家族が全て用意する場合も多くなっています。
絵柄の入った盆提灯は、精霊棚(盆棚)やお仏壇の両脇に一対、二対と飾ります。飾るスペースがないときは、片側に一つだけ飾る場合もあります。
新盆用の白提灯は、玄関や縁側の軒先や、仏壇の前に吊るします。白提灯はローソクの火を灯せるようになっていますが、危ないので火を入れないで、ただお飾りするだけで迎え火とする場合も多いです。
新盆用の白提灯は、一つあればよいです。
●お盆が終わった盆提灯
新盆用の白提灯は、むかしは送り火で燃やしたり、自宅の庭でお焚き上げしたり、菩提寺に持って行き供養処分してもらいました。
しかし最近では、火袋に少しだけ火を入れて燃やし(形だけお焚き上げをして)、鎮火を確認してから新聞紙などに包んで処分する場合が多くなっています。
普通の絵柄の入った盆提灯は、毎年飾るものですから、お盆が終わったら、火袋をよくはたき、部品をきれいに拭いて箱に入れて保管します。
防虫対策に、防虫剤を一つ入れると安心です。
●キュウリの馬・ナスの牛
お盆の時に、ご先祖や故人の霊の乗り物として、キュウリの馬と、ナスの牛を供える場合があります。
これは霊が馬に乗って一刻も早くこの世に帰り、牛に乗ってゆっくりあの世へ戻って行くように、との願いを込めたものといわれています。
真菰(まこも)で作られた馬と牛を供える場合も多いです。
●盆踊り
最近では宗教的な色合いは薄れてきましたが、元来盆踊りは、お盆に帰って来たご先祖や故人の霊を慰め、無事に送り帰すための宗教的な行事でした。
また、帰って来た霊が供養のおかげで成仏できた喜びを、踊りで表現しているともいわれています。
★盆 提 灯
--------------------------------------------------------------------------------------------
 ● 盆提灯はなぜ飾るの?
● 盆提灯はなぜ飾るの?
お盆提灯はお盆のときに、ご先祖や故人の霊が迷わず帰って来る目印として飾ります。
お盆提灯には迎え火、送り火の役割があります。
またお盆提灯は、お世話になった故人の冥福を祈り、感謝の気持ちを表すものです。
親戚や故人と親しかった方々は、故人の供養のためにお供え物をしますが、お盆提灯はお供えとして最高のものとされています。
● 盆提灯はいつから飾ったらよい?
盆提灯には迎え火、送り火の役割がありますので、7月13日(8月13日)に明かりを灯し、16日には明かりを落とします。実際にはお盆月の7月(8月)に入って早い時期から盆提灯を飾る場合が多いです。
● 盆提灯の種類は?
盆提灯には、上から吊るす御所提灯(ごしょちょうちん)、下に置く大内行灯(おおうちあんどん)、霊前灯などがあります。
御所提灯には、絵柄の入った提灯、無地の新盆用の白提灯があります。
大内行灯には、火袋の中が回転するもの、回転しないものがあります。
それぞれの提灯の火袋は、和紙を貼ったもの、絹を貼ったものがあります。
提灯の火袋に家紋を入れる場合もあります。
● 盆提灯はどこに飾るのですか?
絵柄の入った盆提灯は、精霊棚(盆棚)やお仏壇の両脇に一対、二対と飾ります。飾る場所が狭いときは、片側に一つだけ飾る場合もあります。
最近は場所が狭いご家庭が多いので、良いものを少なく飾る傾向にあります。
新盆用の白提灯は、初めて故人の霊が家に帰る目印として、玄関や縁側の軒先に飾りますが、最近は防犯上の心配もあり、仏壇の置いてある部屋(仏壇の前方)に飾る場合も多いです。
白提灯はローソクの火を灯せるようになっていますが、危ないので火を灯さないで、ただお飾りするだけで迎え火とする場合も多いです。
新盆用の白提灯は、一つあればよいです。
● 盆提灯はどうやって選べばよいですか?
盆提灯は、飾る場所や広さを考慮に入れて選びます。
最近は場所が狭いご家庭が多いので、良いものを少なく飾る傾向にあります。
贈る場合は、自分の好みだけでなく、先方の飾る場所や広さも考慮に入れ、後は自分の予算に合わせて選びます。一つでも一対でも、どちらでも失礼にはなりません。
● 盆提灯は親戚でなくても贈ってよいですか?
盆提灯は、故人の供養だけでなく、お世話になった方への感謝の気持ちを表すものですから、親戚でなくても盆提灯を贈るのは大変よいことです。
● 新盆の家庭は白提灯以外は購入してはいけませんか?
故人が亡くなって四十九日の後、初めて迎えるお盆を新盆といいます。
新盆には、普通の絵柄の入った盆提灯のほかに、白い新盆用の提灯を飾ります。この白提灯を飾るのは新盆の時だけで、お盆が終わったら燃やして処分します。
むかしは、新盆用の白提灯は故人のご家族が購入し、普通の絵柄の入った盆提灯は、兄弟、親戚などから贈られていました。
しかし最近では、盆提灯を飾るスペースなどの住宅事情を考えて、兄弟、親戚などから盆提灯用にと現金で頂戴して、故人のご家族が全て用意する場合も多くなっています。
もちろん普通の盆提灯が親戚などから贈られない場合は、自分で用意する必要があります。
● お盆が終わった盆提灯は?
新盆用の白提灯は、むかしは送り火で燃やしたり、自宅の庭でお焚き上げしたり、菩提寺に持って行き供養処分してもらいました。
しかし最近では、火袋に少しだけ火を入れて燃やし(形だけお焚き上げをして)、鎮火を確認してから新聞紙などに包んで処分する場合が多くなっています。
普通の絵柄の入った盆提灯は、毎年飾るものですから、お盆が終わったら、火袋をよくはたき、部品をきれいに拭いて箱に入れて保管します。
防虫対策に、防虫剤を一つ入れると安心です。
● 盆提灯は毎年飾るのですか?
盆提灯には迎え火、送り火の役割がありますので、毎年お盆に飾ります。
ただ、たくさん頂いた盆提灯を毎年飾るのが大変な場合は、2~3年後に少しずつ飾る数を減らしていきます。
● 盆提灯は宗派によって違いますか?
盆提灯は、宗派による違いはありません。むしろ、地域によって飾る盆提灯の種類が違う場合があります。
● 盆提灯は亡くなった人がいなければ飾らないのですか?
盆提灯はご先祖のためものです。どの家庭もご先祖がいるから今日あるわけで、ご先祖を供養し、仏さまに感謝するために盆提灯を飾るのはよいことです。
● 葬儀に使用した提灯をお盆にも使用してもよいですか?
葬儀の後の四十九日まで、盆提灯に似た提灯を飾る場合がありますが、これは故人が安らかに成仏することを願って飾るものです。
盆提灯は、ご先祖や故人の霊を迎え供養するために飾りますので、区別して使用する場合が多いです。
● 盆提灯の取扱い注意は?
吊り提灯は火袋の中にローソク立てがついていますが、ローソクに火を灯した場合は、危険ですのでその場所を離れないでください。実際には火を灯さないでお飾りすることをおすすめします。安全のためにローソク電池灯もあります。
火袋を無理に広げたりしますと、破れてしまう場合がありますので注意してください。
置き提灯はコンパクトな紙箱に入っており、誰にでも簡単に組み立てることができます。
置き提灯は3本足の1本を前にして、火袋の絵柄が正面にくるように飾ります。
置き提灯は下の安定した水平なところでお飾りください。
回転行灯の回転筒が回る原理は、電球の発熱による空気の流れを利用していますので、回転筒が電球や柱に接触しないよう注意してください。お部屋の空調設備の条件によって回りにくくなる場合があります。
電球は緩まないように、しっかりソケットに締めてください。使用後は熱を持ち火傷の恐れがありますので、熱が冷めてから行ってください。
盆提灯の火袋は天然素材のため虫食いにご注意ください。虫が火袋を貼った糊を食べに来ることがありますので、使用後は火袋をよくはたき、部品をきれいに拭いてから箱に入れて保管します。防虫対策に、防虫剤を一つ入れると安心です。
★数 珠
--------------------------------------------------------------------------------------------
 ● 数珠とは
● 数珠とは
数珠は、お葬式や法事、お墓参りの時に手にする最も身近な仏具です。
常にこれを持って仏さまに手を合わせれば、煩悩が消滅し、功徳を得られるといわれています。
数珠は合掌する手に掛け、仏さまと心を通い合わせる大切な法具で、忘れてはならない必需品です。ですから、どの宗派でも数珠を大切にします。
また数珠は、お経や念仏を唱える時に、その数を数えるためにも使われます。
珠数とも書きますし、念珠とも呼ばれます。
数珠は、一連、二連と数えます。
● 数珠の起源
「仏説モクケンシ経」には、お釈迦さまが「国の乱れを治め、悪病を退散させるには、モクケンシの実を108繋いで仏の名を念ずればよい」と語ったことが説かれています。
モクケンシの実とは、羽子板の羽根の球に用いられるムクロジの実のことです。
しかし実際には、数珠はお釈迦さまの時代の前から使われていたようです。
仏教が日本に伝来したとき、数珠も一緒に入ってきました。
正倉院には、聖徳太子が愛用された蜻蛉玉(とんぼめ)金剛子の数珠や、聖武天皇の遺品である水晶と琥珀の数珠二連が現存しています。
すなわち、天平年間には数珠が伝えられていたことになります。
数珠が仏具として、僧侶以外の一般の人々にも親しまれるようになったのは、鎌倉時代以降のことです。
● 数珠の功徳
数珠は、持っているだけで功徳があるとされ、災いを取り除き、平穏や安らぎを得られるといわれています。
信濃の善光寺では、ご上人が本堂に参詣されるときの途上、道にしゃがんでいる信者たちの頭を数珠でなでる「御数珠頂戴」の行事が毎日行われています。
これも数珠の功徳をいただく風習です。
● 数珠の珠の数
数珠は多くの珠を繋いで輪にしたもので、珠の数は108個のものが正式とされ、宗派によって形が異なります。
108珠の由来は、108の煩悩を消滅させる功徳があるからだといわれています。
この正式な数珠を、本連(ほんれん)数珠とか、二輪(ふたわ)数珠といいます。
それに対して、現在では持ちやすくする為に珠の数を減らした、略式の数珠が一般的によく使われています。
略式の数珠は、18~43個くらいの珠で作られていて、大きい珠の場合は数が少なく、小さい珠の場合は数が多く、数に決まりはありません。
この略式の数珠を、片手(かたて)数珠とか、一輪(ひとわ)数珠といいます。
すべての宗派でお使いいただけて、珠の種類や房の形も宗派による決まりはありません。
● 数珠の形
略式の数珠は、珠の大きさによって、男性用数珠と女性用数珠に分けられます。
男性は大きい珠の数珠を、女性は小さい珠の数珠を使うのが一般的です。
正式の数珠は、宗派によって形が異なります。
一般に使われているものは、108個の主玉(おもだま)と、2個の親玉(おやだま)をつなぎ、その親玉に弟子玉(でしだま)と露玉(つゆだま)と房をつけます。
主玉の間に、やや小さい玉を4個入れますが、これを四天玉と呼びます。この玉は、略式の数珠では2個なので、二天玉と呼びます。
真言宗で用いる数珠は、その形から振分数珠とも呼ばれ、真言宗以外の宗派でも用いるので八宗用ともいわれます。
日蓮宗で用いる数珠は、真言宗が両方の親玉に二つずつの房があるのと違って、片方の親玉に三つの房があります。
浄土宗では、二つの輪違いのものに丸環がついている、輪違い数珠が多く用いられます。
天台宗では、平玉の数珠が多く用いられます。
曹洞宗で用いる数珠は、丸環がついています。
● 腕輪念珠
数珠は、念珠ともいわれる最も身近な仏具ですが、いつも手に持っているわけにはいきません。そこで考え出されたのが腕輪念珠です。
厄除けや所願成就のお守りとして、手首につける念珠です。
房があるものと、房なしのブレスレットタイプの2種類があります。
腕輪念珠においては、男女の区別はありません。
● 数珠の素材
数珠の素材は大きく分類して、木の珠と、石の珠があります。
珠の素材は、宗派による決まりはありませんので、お好みで選べます。
[木の珠(木の素材、木の実)]
木の素材には、黒檀、紫檀、鉄刀木(たがやさん)、白檀、つげ、梅などがあります。
木の実には、星月菩提樹(せいげつぼだいじゅ)、金剛菩提樹(こんごうぼだいじゅ)などがあります。
菩提樹(ぼだいじゅ)は、お釈迦さまがその下で悟りを開かれたという木で、その実でつくられた数珠は昔から尊ばれ、経典にも「無量の福、最勝の益を得る」と説かれています。
特に星月菩提樹は、数珠に使われる代表的な木の実で、珠の表面に細かい斑点があり、星を象徴する小さな穴と、月を表す穴があります。
また、羅漢や骸骨を彫った数珠や、お寺の改築のときに出た古材で加工された数珠を記念品として配ることもあります。
[石の珠(宝石、貴石)]
石の種類には、水晶、メノー、ヒスイ、サンゴ、オニキスなどがあります。
特に水晶は、数珠に使われる代表的な珠で、仏教で言う七宝のひとつに数えられています。
弘法大師が師匠の恵果阿闍梨(けいかあじゃり)から伝授された数珠も水晶で、経典にも「あらゆる報障を除滅し、一切の悪業染着すること能わず」と説かれています。
● 数珠の房
数珠の房の形には、梵天(ぼんてん)房、頭付(かしらつき)房、紐(ひも)房などがあります。
梵天房は、放射状に伸びた糸の先端を丸く切り揃えたものです。
頭付房は、編み込んだ頭がついている撚(よ)り房です。
紐房は、打紐をそのまま房としたものです。
房の材質としては、正絹と人絹があり、正絹の方が良いものになります。
正絹とは混じり物のない絹で、人絹とは人造の絹のことです。
房の形や色は、宗派による決まりはありませんので、お好みで選べます。
● 数珠の品質
数珠の珠は、同じ素材でもさまざまな品質があります。特に石の素材は、細かい内傷や表面の加工、色の均一さなどが品質を左右します。
また珠の穴の仕上げも、数珠の品質の重要なポイントです。
数珠の房や中通しの糸、仕立て方にも良し悪しがあります。
良い珠を選別し、良い糸を使い、丁寧な仕立てをすれば、質の良い数珠ができる代わりにコストは上ります。
逆にあまりにも安い数珠には、何らかの理由があると考えなくてはなりません。
● 数珠の扱い方
数珠は、お経を唱えたり、仏さまを礼拝する時、故人を偲び供養する時に、手にかけてお参りします。
合掌する時は、左手にかけて右手を添えるように合わせるか、合わせた両手にかけます。
使わない時は、房を下にして握って持ちます。


● 日蓮宗の数珠の扱い方
日蓮宗のお数珠は、大きな珠(親珠)2個、小さな珠(四天珠)4個、普通の珠108個。合計114個の珠からなっています。
大きな珠は親珠(拇珠)といい、右の親玉を浄名珠といい「釈迦牟尼仏」、左の親珠は数珠を留めるところから、緒留ともいい「多宝如来」をあらわしています。
小さい珠は4天珠といい、上行・無辺行・浄行・安立行の四菩薩をあらわしています。また、左側にある3本の子珠の形の違うもの(10個の子珠)が独特の「数取り」と呼ばれるものです。
● 日蓮宗の数珠の扱い方
仏事のときには、必ずお数珠をもって行きましょう。
日蓮宗のお数珠は、合掌をしたりお経本を持つとき数珠を二重にして房を下にし、左手に掛けて持ちます。
勧請・唱題・回向の時には、親珠を両方の中指の第1関節に、数珠を一度ねじってから(あやにする)そのまま両手を自然に合わせます。
数珠の房は二つ房の方を右手に、三つ房が左手にくるように持ちます。
「右手」み・ぎ =2本(二つ房)
「左手」ひ・だ・り=3本(三つ房)
と覚えるとよいでしょう。
数珠をすり合わせて音を出すのはやめましょう。
合掌は手のひらを隙間なく合わせることです。両手を合わせてほかに何もできないことを示し、一心に祈る礼拝の姿です。
インドでは、右手は清浄(神聖)、左手は不浄(凡夫)を表します。この二つの心が帰依(南無)することによって、仏さまと私たちが一つになれるといわれています。
★お彼岸とお墓参り
--------------------------------------------------------------------------------------------
 ●お彼岸とは・・・
●お彼岸とは・・・
「暑さ寒さも彼岸まで」といわれるようにお彼岸は季節のくぎりであります。
春分・秋分の日が、太陽が真東から上がって真西に沈むことから、西方極楽浄土の信仰と結びついた日本独自の仏教行事です。
昔から、お彼岸にはご先祖の供養のために、お墓参りをする風習があります。
その理由の一つは、「彼岸」という言葉を「あの世」と解釈して、亡くなられた人々を供養するという意味から、お墓参りをするようになったと思われます。
●お彼岸の期間・・・
お彼岸は、春3月と秋9月の年2回あります。期間は、春分の日と秋分の日を中日(ちゅうにち)として前後3日間の7日間です。そして初日を「彼岸の入り」といい、最終日を「彼岸の明け」といいます。
●お彼岸の供養・・・
お彼岸にはできるだけ家族そろってお墓参りをします。お墓参りに特別の作法はありません。墓石をきれいに洗い、周りも掃除して花や線香をお供えします。手桶から水をすくい、墓石の上からかけて合掌礼拝します。
また、家庭では仏壇を掃除し、花や季節のもの、ぼたもち、おはぎ等をお供えし、ご先祖の供養をします。
●お彼岸のお寺の行事・・・
お彼岸にはお寺で、「彼岸会」の法要が営まれます。
お墓参りの折にはお寺の彼岸会にも参加してご供養をお願いします。
忙しくて時間がない場合でも、本堂のご本尊へのお参りとご住職への挨拶は欠かさないようにしましょう。
●お彼岸の意味・・・
彼岸という言葉は、古代インド語のパーラミター(波羅蜜多)が語源で、意味は「彼の岸へ至る」ということです。煩悩や迷いに満ちたこの世を「此岸」というのに対し、悟りの世界・仏の世界を「彼岸」といいます。
悟りの世界に至るために、仏教には六波羅蜜の教えというのがあります。
[布施](ふせ)他人へ施しをすること
[持戒](じかい)戒を守り、反省すること
[忍辱](にんにく)不平不満を言わず耐え忍ぶこと
[精進](しょうじん)精進努力すること
[禅定](ぜんじょう)心を安定させること
[智慧](ちえ)真実を見る智慧を働かせること
彼岸に行くことを願って、行いを慎むことがお彼岸法要の本来の意味です。
●お彼岸と祝日・・・
「国民祝日に関する法律」によりますと、「春分の日」は「自然をたたえ、生物をいつくしむ」、「秋分の日」は「先祖をうやまい、亡くなった人をしのぶ」と書かれています。まさに仏教の精神そのものであります。
★線 香
--------------------------------------------------------------------------------------------
 ● 線香の功徳
● 線香の功徳
線香は、仏さまへの大事な供養物です。その香りは、仏さまにとどくだけでなく、線香をたく本人はもとより、周囲のだれ彼の区別なくゆきわたる徳をもっています。
それは、仏さまの大慈悲心と同じように四方に無限に広がり、私たちに深いよろこびと信心ごごろをおこさせます。
そして線香は、一度火をともすと燃えつきるまで芳香を放ち続けることから、命あるかぎりの仏さまへの信仰と、自らが物事を行うとき努力し続けることをあらわしているのです。
また、線香は良い香りを放って、時と所の不浄をすべて清める徳をもっています。
ですから身体や心の汚れをはらい、清浄な心で仏さまにお参りするために線香をたくのです。
仏事や葬儀においての焼香は、お仏前を美しく清らかにお飾りさせていただくとともに、敬虔(けいけん)な心をささげる儀式なのです。
● 線香の歴史
我が国のお香の起こりは、聖徳太子の時代、推古天皇3年(595年)に淡路島に香木「沈香」が漂着したと日本書紀に書かれていることにはじまります。
その後、各種の香木が中国から入ってきましたが、聖武天皇の時代、東大寺正倉院に納められた有名な香木「蘭奢待(らんじゃたい)」もそのひとつです。
のちに名香ゆえ、足利義政、織田信長などの時の権力者に、その一部が切り取られています。
またこの時代には、唐の鑑真和上が、仏典とともに香木と薬をたくさん携えて、各種の香料を練り合わせて作る「薫物(たきもの)」の製法を伝えたといわれてます。
足利義政の頃には香道の諸式もたち、めでたいときや季節に応じてそれぞれ焚かれるようになりました。
その後の徳川時代の鎖国政策の影響で、香木の輸入難から上流社会でのみ用いられるようになり、ぜいたくな遊びごとのように伝えられておりますが、本来は精神修養が本筋で、香道は禅と一致し仏教とは切れない縁があるものなのです。
線香の歴史は、現在でも中国や台湾で使われる、竹を芯とした竹芯香に始まるとされています。
日本へは、16世紀末の天正年間に現在見ることが出来るような線香の製法が伝わりました。
香木は高価で貴重なので、少しでも香りが長持ちするようにと、線香が工夫されて、使いやすさもあって家庭や寺院に線香が普及していきました。
● 線香の種類
線香は、主な原料によって「杉線香」と「匂い線香」の二種類があります。
杉線香]
杉の葉の粉末を原料に製造されます。
杉特有の香りのする煙の多い線香で、主にお墓用線香として使われます。
[匂い線香]
椨(たぶ)の木の樹皮の粉末を主原料に、各種の香木や香料を加えて製造されます。
現在広く家庭や寺院で使われている線香です。
外箱の体裁で、進物用線香と家庭用線香に分けられます。
長さの種類はいろいろあり、14センチの短寸、16センチの中寸、25センチの長寸、33センチの大薫香、54センチの中天香、66センチの大天香などがあります。
● 線香の選び方
香りは、人それぞれ好みがありますので、自分の好みに合った香りの線香を選びましょう。
どの線香を選んだらよいか迷っている方は、一番人気のある妙香「はごろもの舞」を一度お試しください。やさしい香りの線香です。
最近は、住宅事情からか煙の少ない線香も人気があります。
● 線香の供え方
まずローソクに火を点し、次に線香をローソクの火で点火し、香炉に立てます。
線香の火は、口で吹き消すのではなく、手であおいで消すようにします。
人間の口は、とかく悪業を積みやすく、けがれやすいものなので、仏に供えた火を消すには向かないからです。
ローソクの火を消す場合も同じです。
お供えする線香の本数は、一般的には1~2本ですが、正式には各宗派で異なります。
浄土宗、臨済宗、曹洞宗、日蓮宗は1本で、天台宗と真言宗は3本です。香炉に立てるときは、まとめないで1本ずつたてます。
真宗大谷派と浄土真宗本願寺派は、線香を立てません。
線香を適当な長さに折って火をつけ、香炉に横に寝かせます。
● 線香の原料
線香は、香木や香料に松脂(まつやに)などの糊や染料を加えて練ったものです。
主な原料には、次のようなものがあります。
[白檀(びゃくだん)]
インド、東南アジアなどで産出する常緑樹で、特にインド南部産のものが良質で老山(ろうざん)白檀と呼ばれています。
木材そのものが香るため、仏像、数珠、扇子などにも使われます。
「栴檀(せんだん)は双葉より芳し」の栴檀は、この白檀のことです。
[沈香(じんこう)]
東南アジアに産出するジンチョウゲ科の樹木内に、長い年月を経て樹脂が蓄積したものです。
水に沈むので沈香といわれます。
[伽羅(きゃら)]
沈香の最上の種類。
ベトナムの限られたところから産出され、古くから品位の高い最上の香りと珍重されています。
そのほかの原料としては、椨(たぶ)、丁子(ちょうじ)、桂皮(けいひ)、大茴香(だいういきょう)などがあります。
● 花街の線香代
花街では、芸者さんの花代のことを線香代といいます。
これは、線香1本がともる間を単位に、時間を計算したからです。
その線香は、帳場に置いた大きい香炉に立てていましたので、帳場のことを線香場とも呼んでいました。
● お香の種類
線香以外に仏事で使われるお香には、次のようなものがあります。
[焼香]
香木などの天然香料を細かく刻んで調合したお香です。
使用する香木や香料の数によって、五種香、十種香などと呼ばれています。
仏前で、直接炭火の上に薫じます。
[抹香]
非常に細かい粉末のお香で、長時間くゆらせておく寺院の常香盤や密教用具の火舎香炉などに使われます。
[塗香]
最も粒子の細かいお香で、片栗粉のようになめらかです。
俗に清め香ともいわれ、主に密教寺院などで本尊に供えたり、少量を手や身体に塗って心身を清めるために使われます。
● 香典の意味
もともと香典というのは、霊前に供えるお香の料(代金)です。昔はお香を持参したのですが、喪家側で用意するようになったために、その代金として現金を包んで持参し、霊前に供えるようになりました。
地位のある人には、現金では失礼とする考え方もありましたが、現在では不時の出費に対する相互扶助の意味合いも強くなり、現金を包むことが一般的になっています。
● お線香をあげる本数は一本・1本?三本・3本?
一本の線香に心を込めて仏さまにお供えしても喜ばれるそうですし、三本の線香の場合、仏(お釈迦様)法(その教え)僧(その教えを正しく伝えるもの住職他)三宝に感謝して使う場合、過去・現在・未来へ供養する場合、「仏様の数だけ」供養する場合もございます。
有縁仏・無縁仏・ご本尊様にお供えする、人間の貪り・怒り・愚かさの三悪を懺悔するために線香は三本ともいわれます。
人間と同じように仏様の大切な日には仏様をお祝いする線香『仏様の好物甘茶香』で祝ってあげると喜ばれるでしょう。
お寺さまも線香の本数は一本でも三本でも良いとおっしゃいます。線香の本数や香りを仏様は頂いている訳ではありませんので『線香の本数や仕方に関係なくこの『心』が諸仏諸菩薩を供養し、ひいてはご先祖様の世界にも届きますようにと皆が幸せになれますようにと真心込めて使ってあげると善いそうです。』
★位 牌
--------------------------------------------------------------------------------------------
 ●位牌とは
●位牌とは
位牌とは、死者の戒名、法名を記した木牌のことです。
用途別に分類すれば、葬儀の時に使用される白木の野位牌、四十九日の忌明け後に仏壇に祀られる本位牌(塗位牌、唐木位牌)、寺院内や寺院位牌堂で用いられる寺院位牌などがあります。
仕様で分類すると白木位牌、漆を塗り金箔や金粉などで加飾した塗位牌、黒檀や紫檀などで作られた唐木位牌などがあります。
形式で分類すると、台座に札板が付いた板位牌、台座に板が数枚入った箱が付いている回出位牌(くりだしいはい)などがあります。
位牌は、中国儒教で先祖祭祀の時に使用される位版(いはん)、神主(しんしゅ)などに起源があるとされます。
この儒教儀礼の影響を受けた禅宗が鎌倉時代日本に伝わり、それと共に位牌が日本でも使われるようになったといわれます。
本位牌には、戒名、没年月日、俗名、年齢などを記します。
●白木の位牌と本位牌…
お仏壇に安置される位牌は、本位牌と呼ばれ、黒漆塗りの塗り位牌や黒檀紫檀の材質の唐木位牌などがあります。
白木の位牌は、葬儀の際に用いる野辺送り用の仮の位牌です。
四十九日までは、故人の霊はまだ行き先が定まらず、さまよっていると考えられており、遺骨、遺影と一緒にあと飾りの祭壇にまつられているのが白木の位牌です。
そして、四十九日が過ぎると成仏して、苦しみのない浄土に行くことができると考えられており、成仏した証として、本位牌に作り替えて仏壇に安置します。
白木の位牌は、四十九日の法要の時に菩提寺にお納めし、新しく作った本位牌はご住職に魂入れをしていただきます。
新しい位牌には戒名の文字入れが必要で、10日間位かかります。
四十九日の法要に間に合わせるために、早めに仏壇屋に依頼しておいた方がよいです。
●本位牌は四十九日までに準備
本位牌は、四十九日までに作るのが一般的です。
四十九日とは七七日(しちしちにち)のことで、死後の霊の行き先が決まる日とされており、この日を境として白木位牌から本位牌に代えます。
仏教の死後観では、四十九日がひとつの境となります。
死後七日ごとに生前の罪障審判があり、七回目、つまり四十九日目の審判で次に生まれ出るところが決まります。
この四十九日間を中有(ちゅうう)と呼びます。
ちなみに三十五日目は閻魔大王のお裁きがあるために、初七日、四十九日と並んで三十五日(五七日)は重要な法要とされます。
有(う)という言葉は、存在するということです。
有情(うじょう)といえば人間のことであり、有縁(うえん)といえば、仏の教えを聞いて悟りを開くことのできる人のことです。
人が生まれて死に、次に生まれるまでの間は「四有」といわれます。
まず受胎した瞬間が「生有(しょうう)」、生まれてから死ぬまでが「本有(ほんぬ)」、死の瞬間が「死有(しう)」、そして死んでから次の生を受けるまでが「中有(ちゅうう)」です。
中有は中陰とも呼ばれ、四十九日の間が中陰であり、七日ごとの審判が終了するので、満中陰とは四十九日のことをさします。
●法要と位牌
位牌が庶民の間に広がったのは江戸時代からで、直接的には檀家制度が位牌普及の原動力となり、檀家制度により檀家は檀那寺(所属寺院)が決められ、先祖供養を行うことが社会の仕組みとして指導されていきました。
この時代、先祖の年忌には僧侶を呼ぶことが広まり、その際の供養具として位牌は欠かせないものとなったのです。
位牌祭祀が先祖供養の中心となった江戸時代中期には、庶民も高位戒名を望むようになり、位牌を中心とした年回忌法要と戒名の付与が、寺院経済を支える基盤となりました。
また、社会制度が安定した江戸時代には家産が生まれ、家督相続の象徴が位牌となりました。葬儀の際の「位牌持ち」は、現在に至るまで家督相続者が担うことが多いです。
●位牌の戒名入れ…
位牌の表面には、戒名と亡くなった没年月日、裏面に俗名と行年(ぎょうねん)(享年(きょうねん))を入れます。
俗名とは生前の名前で、行年(享年)とは亡くなった時の年齢です。
亡くなった没年月日は、裏面に入れる場合もあります。
戒名入れの手法には、機械彫り文字と手書き文字があります。
●なぜ戒名を付けるのか
本来ならば、生前に戒を受けて戒名を授かるのが理想ですが、大半の人は亡くなってから戒名を受けます。
仏教式の葬儀では当然のことながら仏教僧侶が式を取り仕切り、引導が死者に対して渡されます。
「引導を渡す」といえば「縁切り」の代名詞のように使われていますが、俗世間から浄土へと引き導くことが、引導の本来の意味で、僧侶は亡くなった人を葬儀を通じて仏の世界、すなわち彼岸へと送り出します。
仏の世界に往くのに俗名のままでは行けない、ということで死者に戒を授け、戒名を付けることで浄土へと送り出すわけです。
●位牌の形と大きさ…
位牌は故人の象徴であり、亡き人そのものです。
故人にふさわしいものをお選びください。
位牌の形は宗派には関係ありませんので、お好みの形をお選びいただきますが、すでに位牌がある場合は同じ形で揃えることもあります。
位牌の大きさは、仏壇の内部の作りに合わせることが大切です。
位牌が大きすぎて仏壇に入らないということがないように、初めての位牌の場合は、先に安置する仏壇を決めてから位牌の大きさを決めます。
仏壇の種類によりまして内部のつくりが異なりますが、上置型仏壇の場合は、札丈 4寸か 4.5寸、台付型仏壇の場合は、札丈 4.5寸か 5寸の位牌を安置する場合が多いです。
すでに位牌がある場合は、ご先祖の位牌と同じ大きさか、少し小さい位牌を選ぶのが一般的ですが、その家にとって、どの故人を中心に考えるかによって異なってきます。
魂入れをしていただいた位牌は仏壇におまつりしますので、仏壇がない家は、四十九日までに仏壇も必要となります。
●位牌の安置場所…
ご住職に魂入れをしていただいた位牌は、仏壇に安置いたします。
仏壇の中心はご本尊なので、御本尊が隠れない様に、左右か一段低い位置に安置します。向かって右側が上座なので、ご先祖を右から順に並べます。
●夫婦の位牌…
夫婦の場合、一つの位牌に二人の戒名を連ねて入れる場合もあります。
この場合、一般的に夫の戒名を向かって右側に、妻の戒名を左側に入れます。
裏側の俗名も夫の俗名を向かって右側に、妻の俗名を左側に入れることが多いです。
●分家の位牌…
昔は、家長制度で先祖代々の位牌は長男がお守りするというのが習わしでしたが、個人の気持ちを大切にする今では、次男でも三男でも両親の位牌を作り、仏壇を用意することもあります。
また、身内にまだ不幸のない家庭でも、自分の全てのご先祖に感謝する意味で、○○家先祖代々之霊位という位牌をつくる場合もあります。
●古い傷んだ位牌…
位牌は亡き人そのものです。
傷んだ位牌をそのままにしておくのは、故人がかわいそうなので、新しい位牌に作り替えることもあります。
その場合、ご住職に魂を移し替えていただき、古い位牌は菩提寺に納めてお焚き上げしてもらいます。
●古い先祖の位牌…
先祖の位牌が増えて、仏壇に納めることが難しくなってきた場合は、回出位牌(くりだしいはい)(戒名を入れる板が10枚位入る箱型の位牌)に作り変えることができます。
また、先祖代々の位牌を作ったり、過去帳にまとめるなど、いろいろな方法がありますので、仏壇屋に相談するとよいでしょう。
「よく知らない古い先祖の位牌がたくさんあるので、整理したいのでどうしたらよいか?」等、位牌に関することは、なんでもお気軽にお問合わせください。
●位牌のいわれ…
位牌は、中国の儒教で先祖や両親の在命中の位官や姓名を板に記してまつった位牌が、日本に禅宗と一緒に伝えられ、各宗派でも使われるようになったと言われています。
浄土真宗では教義上の理由で、位牌は原則として用いません。
過去帳や法名軸が位牌の代わりとなりますが、実際には、浄土真宗の家でも位牌がまつられている場合が多いようです。
●戒名とは…
戒名とは元来、仏教者として守るべき生活や心の規範を受けた者に対して授けられる名前です。現在では亡くなってから戒名が授けられるというのが一般的ですが、本来は生きている間に戒を受け、仏教者としての生活を送ることが理想であり、実際に大半の寺院では、生前に戒名を授けること(生前戒名)を行っています。
また、仏の弟子なったことをあらわす名前です。
戒とは仏弟子として守らなければならない戒律のことで、生きている人が出家して仏門に入り、仏教の多くの戒を受けた者にあたえられる名前です。
現在では亡くなった故人をたたえ、仏弟子として仏の浄土に往生するために、葬儀の前にご住職につけていただき、故人の象徴とします。
浄土真宗では、法名といい、日蓮宗では法号ともいいます。
位牌に書いてある文字全体(院号・道号・戒名・位号)を戒名と呼んでいますが、正式には生前の俗名や経典にちなんだ二文字で表されます。
どんな身分の人でも二文字で、仏の世界では平等であることが表現されています。
また○○院という院号は、本来は生前に一寺を建立するほど寺院につくすなど、社会的に高い貢献をした人につけられるものです。
★日蓮宗の仏壇
--------------------------------------------------------------------------------------------
 仏壇は、私たちを守って下さってる仏さま、ご先祖さまをおまつりする家庭信行の大切なよりどころです。本家、分家、長男、次男に関係なく、各家庭におまつりいたしましょう。
仏壇は、私たちを守って下さってる仏さま、ご先祖さまをおまつりする家庭信行の大切なよりどころです。本家、分家、長男、次男に関係なく、各家庭におまつりいたしましょう。
1、ご本尊
お仏壇には必ずご本尊(お曼荼羅)と日蓮聖人像をおまつりします。
2、お位牌
お位牌は、ご本尊の両脇かその下の段におまつりします。
3、過去帳
ご先祖の法号・俗名・ご命日を書き入れます。
4、五具足
五具足は香炉・花一対・ローソク一対で5つになります。三具足は香炉・花・ローソクで3つになります。
5、お供物
お茶・お水・仏飯を供えます。
★ 神 棚
--------------------------------------------------------------------------------------------
 ● 神様まつり
● 神様まつり
古来より日本の家庭では、ご先祖様を仏壇におまつりして身近にお守りいただき、また、全国の総鎮守である伊勢の天照皇大神宮、地域の守り神である氏神様、その家に係わる神様方を神棚におまつりしてきました。
家族の安泰や幸せを願い、大自然の生み出す四季や家族の絆を感じ、日頃の生活に感謝し、折々に神様まつりがおこなわれてきたのです。
神棚をお参りすることで、毎日の生活への感謝の気持ちや願いごとを、御神札(おふだ)を通して神様にお伝えし、日々そのご加護をいただいているわけです。
● 神棚には何をおまつりするのか
神棚には、神社から頂いた御神札(おふだ)をおまつりします。
御神札は、伊勢の天照皇大神宮の御神札が祭祀の中心となります。
神棚の中央に伊勢の天照皇大神宮の御神札、向かって右に氏神様の御神札、左にその他の信仰している崇敬神社の御神札をおまつりします。
重ねる場合は、一番手前に天照皇大神宮の御神札、その後に氏神様の御神札、その他の信仰している崇敬神社の御神札という順番にします。
台所に、荒神様の御神札をおまつりすることも行われています。
御神札(おふだ)は、年末に毎年新しく氏神様の神社でお受けして、一年間おまつりした古い御神札は、神棚をお掃除した後、いただいた神社に納めます。
● 神様の種類
[お伊勢様]
天照大御神(あまてらすおおみかみ)は、孫に当たる邇邇藝能命(ににぎのみこと)に言いました。
「豊葦原(とよあしはら)の瑞穂(みずほ)の国は、私の子孫が治める国です。
私の孫であるあなたが行きなさい。
そして、天の神の子孫を中心とする国は、天地の道理にかない、いつまでも栄えることでしょう。」
という神話があります。
天照大御神は、日本の国を初めて治める事を命じられた神様で、現在においては三重県伊勢にまつられ、
全国の総鎮守と仰がれる神様です。
伊勢の神宮は、皇大神宮(こうたいじんぐう)(内宮(ないくう))と豊受大神宮(とようけだいじんぐう)(外宮(げくう))を
中心とする日本で最も貴いお宮です。
天照大御神をおまつりする「内宮」は、皇室の御先祖神として尊ばれ、豊受大御神をおまつりする「外宮」は、
五穀豊穣、衣食住の守り神として崇(あが)められています。
天照皇大神宮の御神札は、大麻(たいま)とも呼ばれています。
[氏神様(うじがみさま)]
その人の住む土地の鎮守の神様で、その地域の土地、建物、家々、各々に至るまで、毎日の生活をお守りいただく神様です。
その地域で生まれた方や、居住されている方、その土地に会社や商店を構える方々を氏子と称しています。
[崇敬(すうけい)神社]
お伊勢様、氏神様の他に個人や会社に特に御縁のある神様です。
[荒神(こうじん)様]
竈(かまど)の神様で、台所の安全など火に関係する場所をお守りいただく神様です。
● 天地の恵み
お伊勢様は、皇室のご先祖の神様であり、また私たち国民の総氏神様でもあります。
その広大無辺のご神徳は太陽にたとえられ、「天の恵み」と仰がれます。
氏神様は、都会にあっては諸産業を、農村にあっては農業を守護するなど、その土地に暮らす全ての人々(氏子)と、その生活をお守りくださる、最も身近な神様です。
親が我が子を慈しむような、大地が五穀を育むようなそのご神徳は、「地の恵み」と称えられます。
この世に生きる全てのものは、天地の恵みによって生かされ、神々のご守護によって生活を営んでいます。
すなわち、お伊勢様の「天の恵み」と、氏神様の「地の恵み」とがあたかも車の両輪のごとくひとつとなって、より尊いご神威があらわれ、より一層のご守護をいただけるのです。
ですから、お伊勢様と氏神様の御神札をおまつりして、私たちは国の隆昌と家庭の幸せをお祈りするのです。
お正月を迎えるにあたり、神棚をお掃除して、お伊勢様と氏神様の御神札を新しいものに取り換えます。
これは、より新しいお力、より新しい生命をいただくという意味があり、日本の伝統、先祖伝来の美しい風習です。
● なぜ神棚をおまつりするのか
神棚には日本の神様や仏教と習合した神様をおまつりします。
日本の神様は神話の時代から続く我々日本人の祖先であり、神棚の祭祀はそうした遥か遠くの祖先をおまつりすることになるのです。
また日本の神様は天照大御神が太陽神であるように自然の象徴であることが多く、神棚祭祀は自然への感謝と畏敬を表す場所ともなります。
日本の宗教風土は仏と神が混然一体となった歴史を持ち、遠い先祖を神様と崇(あが)め、近い先祖を仏様と尊び、現代にいたるまでその習慣は続いています。
神棚の祭祀により日本が神話から続く歴史をもつことを知り、自然に感謝することはきわめて重要なことであります。
● 神棚とは
日本の神様や仏教と習合した神様をおまつりするための、小型のお宮を神棚と呼びます。
神棚とはお宮と棚の両方を含んだ名称で、棚そのものを神棚ということはほとんどなく、棚をさす言葉としては「棚板」という名称が使われます。
家庭での神棚祭祀が始まったのは江戸時代の初期であり、伊勢神宮への信仰を勧めた御師(おし)達が神宮の御神札を配る中で、その御神札の安置場所としての家庭用神棚の祭祀が始まったと考えられます。
神棚は、粗末にならない清浄な場所で、東向きか南向きにおまつりするのが良いとされています。
神棚を新しくおまつりする時期は、一般的には年末におまつりする人が多いようですが、家を新築した時や商店の開店、事務所開きの時に、新しい神棚を整えて、一家の繁栄、家内安全、商売繁盛、諸願成就を願います。
● お参りの作法
神棚をお参りするときは、まず手を清め、口をすすぎます。
次に、二拝(にはい)(深くお辞儀を二回)、二拍手(にはくしゅ)(手を二回たたく)、一拝(いっぱい)(深くお辞儀を一回)します。
神棚には、扉の正面に鏡をすえて、お米、お塩、お水、お酒、お榊、灯明などをお供えします。
お水は毎朝お供えし、それ以外は毎月一日と十五日に新しいものをお供えします。
注連縄(しめなわ)は、向かって右側に太いほうがくるように掛けます。
★干支による守護本尊とご利益
--------------------------------------------------------------------------------------------
 子年生まれ
子年生まれ
→守護本尊は千手千願観世音菩薩。千の手と眼を持ち、あらゆる願い事を叶えてくださる仏。
丑・寅生まれ
→守護本尊は虚空菩薩。無限の叡智をもち、限りないご利益を授けてくださる仏。
卯生まれ
→守護本尊は文殊菩薩。智慧の象徴とされ、願をすべて成就させてくださる仏。
辰・巳生まれ
→守護本尊は普賢菩薩。災いを避け、信仰する者を正しく導き、悟りに至らしめてくださる仏。
午生まれ
→守護本尊は勢至菩薩。阿弥陀世来の脇侍で、叡智をもって人々の悟りの道へと導いてくださる仏。
未・申生まれ
→守護本尊は大日如来。全ての仏の頂点に立つ存在で、あらゆる霊徳を約束する仏。
酉生まれ
→守護本尊は不動明王。煩悩を打ち払い、仏教を信仰する者に対しては些細な願い事でも叶えてくださる仏。
戌・亥生まれ
→守護本尊は阿弥陀如来。一切の苦難を逃れ、名前を唱えれば、必ず極楽浄土に連れて行ってくださる仏。
★燃費の新旧比較
--------------------------------------------------------------------------------------------


これからの燃費表示は、JC08モードの表記になるようです。
★無線LAN規格
--------------------------------------------------------------------------------------------

 |
 |
| 無線LANは現在おもに3種類の規格が利用されています。では、それぞれの規格にはどのような違いがあり、どのような特長があるのでしょう。 |
 |
| IEEE802.11gと同じく伝送速度が最大54Mbpsの無線LAN規格ですが、こちらの規格は5.2GHz帯を使用します。IEEE802.11gが使用する2.4GHz帯は11Mbps無線LANやBluetoothなど多くの電子機器に使われているため混信やノイズの影響を受けやすく、影響を受けると伝送速度が低下する問題があります。それに対して5.2GHz帯を使用する11aは混信の少ない周波数帯域なのでスムーズな通信が可能です。その一方で周波数が高いために2.4GHz帯に比べると伝送距離が短めで、障害物の影響を受けやすいという弱点はありますが、混信やノイズの多い都市部においては、ノイズに強い11aは安心して利用できる高速無線LAN規格です。 |
 |
| 11aと11gの登場で速度的には高速とは呼べなくなった11bですが、無線LANの急速な普及で11b専用のアクセスポイントやアダプタは非常にリーズナブルな価格になっています。11Mbpsという伝送速度はADSL/CATVインターネット、一般的なデータ交換レベルであれば十分なパフォーマンスを得ることができます。エレコムの無線LANアクセスポイントなら、11a、11gの54Mbpsと11bの11Mbpsの無線LANを同時に利用できるデュアルバンドタイプの製品がありますので、同じネットワーク内でもデータ量の少ないところに11bを導入すれば、コストパフォーマンスもよいネットワーク環境を実現できます。 |
 |
| 従来からある11Mbps無線LANのIEEE802.11bと同じ2.4GHz帯を利用する54Mbps無線LANの新しい規格です。同じ54Mbpsでも5.2GHz帯を利用するIEEE802.11a規格の無線LANに比べて障害物に強く、伝送距離が長いという特長があります。その一方で11gが使用する2.4GHz帯は11Mbps無線LANやBluetoothなど多くの電子機器が使用するため、混信などノイズの影響を受けやすい弱点があります。おもな用途としては障害物の多い環境で高速無線LANを利用したい場合が考えられます。通信方式には11aと同様、OFDM方式を採用しています。 |
| 規格 |
伝送速度
(最大) |
使用周波
数帯域 |
通信
方式 |
特長 |
| IEEE802.11a |
54Mbps |
5.2GHz帯 |
OFDM
方式 |
●周波数が高く、混信やノイズの影響が少ないので、最大速度で通信しやすい。
●周波数が高いために、伝送距離が短め、障害物の影響を受けやすい。 |
| IEEE802.11b |
11Mbps |
2.4GHz帯 |
DS-SS
方式 |
●周波数が低い(2.4GHz帯)ため、電波の特性上5.2GHz帯よりも伝送距離が長い。障害物の影響も受けにくい。
●2.4GHz帯は多くの電子機器が使用するので、混信やノイズの影響を受けやすい。混信やノイズの影響を受けると伝送速度が大幅に低下する。 |
| IEEE802.11g |
54Mbps |
2.4GHz帯 |
OFDM
方式 |
| IEEE802.11n |
600Mbps |
2.4GHz帯
5GHz帯 |
OFDM
方式 |
●2.4GHz帯:屋内外に限らず免許不要
●5.15 - 5.35GHz:屋内の利用に限り免許不要
●5.47 - 5.725GHz:屋内外に限らず免許不要 |
|
|
|
無線LAN基礎知識
★受動喫煙・・・
--------------------------------------------------------------------------------------------

「たばこ」 は 本人よりもまわりの人に害が・・
他人が吸った「たばこ」の煙を吸わされることを、受動喫煙といいます。
たばこを吸わない人(非喫煙者)が、自分の意志と関わりなくたばこの害を受けることになるため、不本意喫煙などともいわれます。
これを防ぐための取り組みが課題となっています。
主流煙より副流煙に !
たばこの煙の中には、約40種類の発がん物質を含む、数千種類の化学物質があります。
たばこの主な有害物質として、習慣性があるほか血管を収縮させて血流を悪くしたり、血管の老化を早めるニコチン、全身への酸素の運搬を妨げる一酸化炭素、発がん物質のベンツピレンやニトロソアミン、そしてダイオキシンまで含まれているのです。
たばこの煙は、その性質により2種類に分けられます。
一つは、たばこを吸う人(喫煙者)が吸い込む主流煙で、もう一つは、火のついた先から出る副流煙です。
主流煙は、燃焼温度の高い部分で発生し、たばこの内部やフィルターを通過するのに対して、副流煙は燃焼温度が低いため、主流煙に比べて有害物質が高い濃度で含まれています (表)。
| たばこの煙に含まれる有害物質 |
| 物質名 |
性質 |
主流煙に対する副流煙の含有量 |
| ニコチン |
有害物質 |
2.8倍 |
| ナフチルアミン |
膀胱発がん物質 |
39.0倍 |
| カドミウム |
発がん物質・肺気腫 |
3.6倍 |
| ベンツピレン |
発がん物質 |
3.9倍 |
| 一酸化炭素 |
有害物質 |
4.7倍 |
| ニ卜ロソアミン |
強力な発がん物質 |
52.0倍 |
| ちつ素酸化物(NOX) |
毒性 |
3.6倍 |
| アンモニア |
粘膜刺激・毒性 |
46.0倍 |
| ホルムアルデヒド |
粘膜刺激・せん毛障害・咳反射 |
50倍 |
(米国健康教育福祉省ほか)
★日本の中心で話題を呼んでいる「謎の鳥」 2010-02-04記事
--------------------------------------------------------------------------------------------

日本には謎の鳥がいる。正体は良く分からない。
中国から見れば「カモ」に見える。
米国から見れば「チキン」に見える。
欧州から見れば「アホウドリ」に見える。
日本の有権者には「サギ」だと思われている。
オザワから見れば「オウム」のような存在。
でも鳥自身は「ハト」だと言い張っている。
それでいて、約束したら「ウソ」に見え
身体検査したら「カラス」のように真っ黒、
釈明会見では「キュウカンチョウ」になるが、
実際は単なる鵜飼の「ウ」。
私はあの鳥は日本の「ガン」だと思う。
実におもしろいことを言う人がいるもんだ。
★良 い 文 章 を 紡 ぐ 5 つ の テクニック
--------------------------------------------------------------------------------------------

1. 使い古された言葉ではなく"自分の言葉で"書く
私たちは本当に豊かな言葉を持っているのです。それをぜひ使ってください! 同僚に宛てて書いていても、まったく見知らぬ人に向けて書いていても、いつでも一番ふさわしい美しい言葉を探すこと。放っておくと、ありきたりの常套句が浮かんでくると思います。でも、「上記のように...」ではなく「私が思ったのは...」と書いたり、「エンドユーザー」ではなく「パソコンを使っている人たち」と書きましょう。比喩的な表現を使う時も「バケツをひっくり返したような雨」なんて使い古された言葉ではなく、「空はどんよりとして、やっかいの種をひっきりなしに落としてくる」など、自分の言葉を使ったオリジナルな表現を探しましょう。
2. 名詞を使う時はよく吟味すること
名詞というのは文章の要です。どの名詞を選ぶかによって、その文章のキャラクター、イメージ、テーマなどが決まってきます。最もイメージにふさわしい、そして正確な名詞を選びましょう。例えば「家」という言葉を使う時、別荘、小屋、二世帯住宅、東屋、古民家、庵、長屋など、色々な選択肢がある中から、「なぜ『家』を選んだのか?」と意識したことはあるでしょうか?
漠然とした名詞を使う時は、細心の注意が必要です(住宅、住居、住まい、居住空間などの抽象的な表現はまた別の話です)。時に、校長先生が保護者の人たちに向かって「コミュニケーションを円滑にする技術は折衝能力を上げるのです」と言ったりしますが、ただ「子どもたちが上手に文章を書けるように助けてあげましょう」と言えばいいのです。相手がきちんと理解できるかどうか、も意識しておくと、よりよく吟味できます。
3. 動きのある動詞を選ぶこと
動詞なんだから動きがあるのは当たり前だろうと思われそうですが、動詞には"静的な動詞"と"動的な動詞"があります。静的なものは、「いる」「ある」「なる」などです。動的なものは、「鳴らす」「しゃべる」「驚く」などです。文章を書く時には、最初は知らないうちに静的な動詞を使ってしまいます。ところが、動的な動詞を織り込むと、途端に文章へ躍動感が生まれます。自分の書いた文章を見直して、ぼんやりとした静的な動詞を外し、イキイキとしたものにしましょう。
4. 曖昧な表現は避けること
名詞をよく吟味すると、無駄な形容詞を使わずに済みます。また、動きのある動詞を選ぶと、無駄な副詞も使わずに済みます。あとは、あいまいな飾り言葉を無くすようにしてみましょう。例えば、「私の頭の中の景色」と「私の想像力」を比べてみてください。余計な修飾語をいくつも使うのはやめて、分かりやすい1つの単語を選びましょう。
5. 書き手の立場に合わせたトーンで
すべての文章は会話と同じです。その文章で、読み手と自分がどのような関係性でありたいのかを明確にしましょう。権威ある作家なのか、流行を先読みする人なのか、賢い友人なのか、どういう立場で書いていますか? 立場や関係性に合わせて、会話のように文章のトーンも変えてください。権威ある立場ならば、凛とした厳然たる言葉で「指示語を使えば、信頼を得ることができるでしょう」。気兼ねない友人のようにしたければ、くだけた言葉で「読んでる人に話しかけたらいいんじゃない?」。読者と同じような立場で言いたければ、"私たち"という言葉を使って「どんな文章を書く時でも、私たちはみな悩んでいるのです」。一度立ち位置を決めたら、決してそれからブレないことです。
★お茶について
--------------------------------------------------------------------------------------------

お茶の淹れ方
○香りを楽しむなら・・・
熱いお湯(90度くらい)でサッと淹れると、香り高い風味に。
○コクを味わいたいなら・・・
少し湯冷まし(80度くらい)をして、急須を軽く揺らして淹れてみましょう。
○濃いお茶を飲みたいなら・・・
少し湯冷まし(80度くらい)をしてから、急須を強く振って淹れると、濃厚なのに苦みがない、深い味わいに。
お茶の保存方法
お茶は、湿気や高温、移り香を嫌います。未開封のお茶は、冷蔵庫または、冷凍庫に保存してください。(冷凍庫に入れた場合は、室温に戻してから開封してください。)開封した後は、密閉できる缶などに入れて冷暗所で保存し、お早めにお飲みください。
茶の十徳
『茶十徳』とは、明恵上人(みょうえしょうにん)がお茶を飲むことの効用を「十ヶ条」に著し広めたもので、お茶を飲めば健康で長生きでき、
神仏に護られて穏やかに臨終を迎えられることが説かれています。
①諸天加護
お茶は強く根をはり、一年中緑を保ちます。その生命力があなたを守ります。
②無病息災
お茶は養生の仏薬ともいわれ、毎日を元気に暮らすことができます。
③父母孝養
お茶の深い味わいは素直な心を芽生えさせ、父母への感謝の心を育てます。
④朋友和合
一服のお茶が楽しい語らいを生み、家族の団らんや友愛の場をかもします。
⑤悪魔降伏
お茶の香気は披露を解消し、心の迷いまでも払拭します。
⑥生心修身
「茶道」として生きている風習は、精神修養の効果があります。
⑦睡眠自除
お茶は、神経を活発にさせ、頭脳と血液の循環を増進します。
⑧煩悩消滅
お茶の深い味わいは、わずらわしい世事の疲れを忘れさせます。
⑨五臓調和
お茶に含まれるたくさんの保健成分が、体全体のバランス維持に役立ちます。
⑩臨終不乱
お茶はその昔、仏薬として珍重されました。愛飲が心の平静を保ち、天寿を全うできます。

 河岸段丘が発達した千葉県君津市の小櫃川・小糸川流域では、飲料水や農業用水の確保が困難でした。江戸時代までの井戸掘りと言えば、人力で竪穴を掘る「掘り井戸」、やがて地中に鉄棒を突き入れる鉄棒式(突抜工法、掘抜工法)が普及しますが、鉄棒式で掘削できるのは深さおよそ20間(約35m)までで、充分な飲料水や農業用水を確保できません。そこで小櫃地区では大村安之助が、小糸地区では池田久吉と池田徳蔵らが中心となり、技術の改良に努めました。
河岸段丘が発達した千葉県君津市の小櫃川・小糸川流域では、飲料水や農業用水の確保が困難でした。江戸時代までの井戸掘りと言えば、人力で竪穴を掘る「掘り井戸」、やがて地中に鉄棒を突き入れる鉄棒式(突抜工法、掘抜工法)が普及しますが、鉄棒式で掘削できるのは深さおよそ20間(約35m)までで、充分な飲料水や農業用水を確保できません。そこで小櫃地区では大村安之助が、小糸地区では池田久吉と池田徳蔵らが中心となり、技術の改良に努めました。 明治19年には小糸地区で、石井峯次郎がハネギを考案し、沢田金次郎がシュモクとヒゴグルマを考案したことにより、明治28年頃には現在の上総掘り技術が完成されたと言われています。
その後、上総掘りは全国に広まり、天然ガス・温泉・石油の採掘などに活用されましたが、昭和40年代には灌漑用井戸の需要減・水道の普及・機械掘りの普及などによって人件費のかかる上総掘りは行われなくなっていきました。
明治19年には小糸地区で、石井峯次郎がハネギを考案し、沢田金次郎がシュモクとヒゴグルマを考案したことにより、明治28年頃には現在の上総掘り技術が完成されたと言われています。
その後、上総掘りは全国に広まり、天然ガス・温泉・石油の採掘などに活用されましたが、昭和40年代には灌漑用井戸の需要減・水道の普及・機械掘りの普及などによって人件費のかかる上総掘りは行われなくなっていきました。


 市の花「コスモス」は、茂原市制施行四十五周年を記念して、市民の方々からの公募提案をもとに、平成9年10月20日に選定されました。
市の花「コスモス」は、茂原市制施行四十五周年を記念して、市民の方々からの公募提案をもとに、平成9年10月20日に選定されました。 「隠れる」という意味の「オン(隠)」という言葉から変化して「オニ」になったといわれている。
「隠れる」という意味の「オン(隠)」という言葉から変化して「オニ」になったといわれている。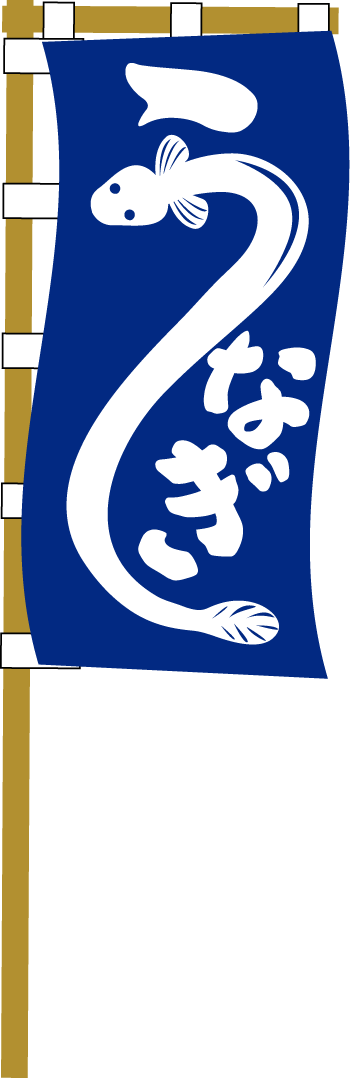 土用の丑の日とは
土用の丑の日とは 東京
欠け始め: 09:53
食最大: 11:08 (食分0.75)
食終了: 12:28
東京
欠け始め: 09:53
食最大: 11:08 (食分0.75)
食終了: 12:28




 案内状や招待状をいただいたときの返信の仕方です。
案内状や招待状をいただいたときの返信の仕方です。 午前0時を子(前後1時間)
午前0時を子(前後1時間)



 ● 盆提灯はなぜ飾るの?
● 盆提灯はなぜ飾るの? ● 数珠とは
● 数珠とは

 ●お彼岸とは・・・
●お彼岸とは・・・ ● 線香の功徳
● 線香の功徳 ●位牌とは
●位牌とは 仏壇は、私たちを守って下さってる仏さま、ご先祖さまをおまつりする家庭信行の大切なよりどころです。本家、分家、長男、次男に関係なく、各家庭におまつりいたしましょう。
仏壇は、私たちを守って下さってる仏さま、ご先祖さまをおまつりする家庭信行の大切なよりどころです。本家、分家、長男、次男に関係なく、各家庭におまつりいたしましょう。 ● 神様まつり
● 神様まつり 子年生まれ
子年生まれ







