![]()
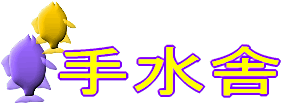
|
|
|
|
|
手水舎は、鳥居をくぐってすぐのところにある拝礼の前に手を洗い口をすすいで身を清める場所のことで、手を洗うことから、「てみずや」と呼ばれています。 古来、神社に参拝する折、近くを流れる川の水や湧き水で手を清めていました。しかし、時代とともに川の水が汚染され、清流や湧き水が確保できなくなったことから、それに代わる施設として境内に御手洗場を設けるようになったのが起こりといわれています。 手水舎は、参拝者の神前に進むまえに手と口を清めるために設けられているものである。 神道の神さまは不浄を嫌う。したがって、神事をおこたったり、神前で祈願をおこなうときには、まず身を清めなくてはならない。これを「みそぎ」(禊・身滌)という。 とはいうものの、やはり参詣のたびに沐浴するのは負担が大きい。手と口をすすぐことによってみそぎに代え、しかもみそぎ場まで行かずにすむようにしたのが、手水舎である。 |
![]()
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
|
|