大黒宮(だいこくみや)
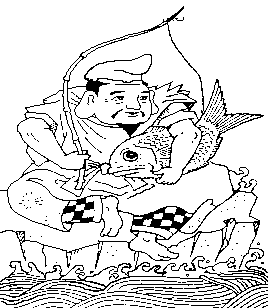

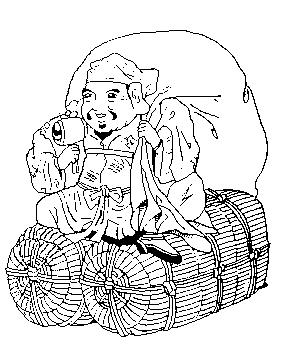
大黒宮の設置場所は、
●目線より高いところ(神様なので見下すことのないように)
●神棚の正面が南か東にくるところ
●扉の上など人が通るようなところは避ける
●明るく静かな正常な場所はにする(トイレはダメ)
大黒様について(ルーツは、ヒンドゥー教の破壊の神、戦闘の神)
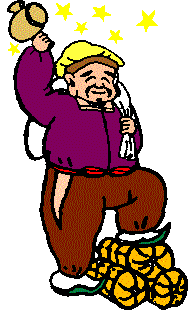
◆元は忿怒の相
大黒さまといえば、左肩に大きな袋を背負い、右手に打出小槌をもち、米俵をふむ、いかにも福々しい姿をおもいうかべるにちがいない。しかし、 このような姿が定着するまでには長い道のりがあった。
そのルーツをたどると、大黒さまはインドの神さまだった。サンスクリット語でマハーカーラと呼ばれ、この音を漢字にすると摩訶迦羅となる。 マハーは大、カーラは黒色を意味する。そこから大黒天と呼ばれる。
大黒天がインドでどのような神だったかというと、ヒンドゥー教の主神の一つシヴァ神の化身で福神のノイメージとほど遠い、青黒い身体を持つ破壊の神・戦闘の神だった。。
その姿はさまざまに描かれているが、戦闘の神というだけに、その形相はすさまじく、髪の毛を逆立て、忿怒相(怒りの表情)をしている。なかには三面八臂(三つの顔に八本の腕)で表現され、 その腕は武器や人間、獣などをつかみ、ドクロの首飾りをしているものもある。大黒天がなぜ青黒い身体なのかは謎であるが、あるインドの伝説によると、 太古に大海がかき乱されたときに、カーラーハーラという毒が出てきて、そのままでは世界が滅びてしまうので、シヴァ神がその毒を飲み込んでしまった。すると首が黒くなったという。
◆台所の神に変身
インドでは、すべての大黒天が恐ろしい姿で表現されていたのではない。唐の僧義浄(635〜713)が書いた見聞録『大唐南海寄帰内法伝』には、 インドの寺院の台所には、金の袋をもち、背丈二尺から三尺(約60〜90センチ)ほどの小柄な体の大黒天が祀られており、いつも油で拭くので、 その身体は黒くなっている、とある。つまり、大黒天には台所の神としての顔もあったのだ。その後、台所の神としての側面は、伝教大師最澄(767〜822)に よって日本に伝えられ、比叡山を中心とした天台宗寺院では、台所に大黒天が守護神として祀られるようになった。
比叡山に最初に祀られた大黒天は三面大黒と呼ばれ、正面に大黒、向かって左に毘沙門天、右に弁財天を配した一風変わったものだったらしい。
いづれにせよ、中国を経由して日本へと大黒天の信仰が伝わっていくうちに、大黒天の恐ろしい形相は次第にマイルドなものに変化していったようだ。
◆大国主命との同一視
大黒天の信仰が一般に広まるようになったきっかけは、大黒天と大国主命の習合によるといわれている。これは、大国主命の大国と大黒の音が通じ合うことから、 両者が同一視されるようになったことにもよるが、仏教側(特に天台宗)からの働きかけもあったと考えられる。
十四世紀に書かれたとされる「三輪大明神神縁起」によると、最澄の前に大黒天に姿を変えた三輪大明神が現われたとされている。 三輪大明神は大国主命を祀っており、そこから大国主命=大黒天という図式がでてくる。このように中世には、仏教と神道を近づけるために、 「縁起」と呼ばれる神仏の由来書が多く書かれた。
大黒天の信仰の普及に一役かったのが大黒舞と呼ばれるもので、大黒頭巾をかぶり、手には打出小槌をもって、大黒天に扮して舞う祝福芸である。 中世のなかごろから行われていたらしいが、「一に俵をふんまえて、二ににっこり笑うて、三に盃いただいて、四に世の中良いように〜」という めでたい数え歌を歌いながら、毎年正月に各地の家々をまわり、大黒天の福をわけあたえるのである。
◆カマドの神から福の神
大黒天の信仰が広がると、台所の神さまとしての側面は、台所の中心となるカマドを守ってくれる神さまということで、カマド神の側面ももちはじめる。 大黒天が踏む米俵に象徴されるように、農村では田の神としての役割もはたすし、商家では商売繁盛の神さまという役割もはたすようになる。
大黒天の背負う袋は、まさに福袋であり、そこからでてくる御利益はつきないようにみえる。
日常生活でよく使われる「大黒柱」とは、家のなかで中心となる柱のことで、そこから転じて、家族を支えて中心となる人のことをさすが、 それがなぜ「大黒柱」というのだろうか。
かって家を建てるとき、土間と座敷の間に中心となる柱が立てられ、そこに大黒天を祀ったからである。この柱は台所にも隣接しており、台所の神という条件もみたしてくれる。 そこから「大黒柱」という名前がついたのである。
恵比寿様について(商売繁盛の福の神は、漁民の信仰から始まった)

◆海から来る神霊
エビスは釣竿を持ちタイを抱えた福々しい姿の福神で、関西では「えべっさん」の愛称で親しまれている。
エビスには夷・戎・恵比寿・恵美須などの字があてられ、その語源は、異邦人や辺境に住む人々を意味するエミシ・エビスの語に由来するとされている。おそらく、生活空間の外部にある異郷から福をもたらす神としてイメージされていたらしい。
その姿があらわすように、もともtエビスは漁民のあいだで信仰されはじめたと考えられる。漁村では、大漁をもたらす神として、海岸や岬の祠に祀られることが多く、 毎年漁の初めに、船主や村の若者が目隠しをして海底に入り、拾ってきた石を御神体として祀る例もある。また、鯨・鮫・イルカや海中から拾い上げた石、海岸に流れついたものまでエビスと呼んで祀る例もある。
さらに興味深いことに、海岸に流れついた水死体までもエビスと呼び、大漁を呼ぶものとして信仰される例もある。海のかなたに常世の国(ユートピア)があるとされ、 海から来る神霊が大漁をもたらすと考えられたからだろう。
◆大漁の神から商業神に変身
漁業の神としてのエビスは、中世における商業の発展とともに、商業神としての性格をもちはじめる。古くは、長寛元年(1163)に奈良東大寺内に、建長五年(1253)には鎌倉鶴岡八幡宮に、 市の守護神として祀られているが、それが商業の発展とともに商人の信仰を集めるようになった。 エビスの信仰が海から陸へと伝わり、商業神の性格をもつように背景としては、西宮神社(兵庫県西宮市)を本拠地とする、夷舁(えびすかき)あるいは夷まわしと呼ばれる 漂泊の芸能民が重要な役割を果たしたとされる。
彼らは、人形舞を演じながら各地をまわり、エビスの御利益を宣伝するとともに、エビスの像を印刷した御札を売ってまわった。
商売の神様としてのエビス信仰の中心は西宮神社で、その祭神は蛭児大神とされている。
ヒルコ(蛭児)というのは、記紀によると、イザナギ(伊弉諾)とイザナミ(伊弉冉)の間に生まれた子で、身体に障害があり、三歳になっても立つことができず、 葦の船に乗せて流されたとされる。記紀のなかでは、蛭児のその後は行方不明になっとされているが、それが浜に流れついて西宮神社の祭神になったのだという。
海の彼方からやってくるというイメージが、ヒルコとエビスに共通するからか、次第にヒルコとエビスは同一視されるようになったと考えられる。 そこから、西宮神社の祭神である蛭児大神は、別名夷三郎様と呼ばれている。しかし、夷と三郎というのも、もともと別の神だったらしい。 三郎というのは、(一般には因幡の白兎の物語で知られている)大国主命の子である事代主命のことだとされ、彼が出雲の美保崎で魚を釣ったという伝承から、 魚と釣竿を持った姿で描かれるようになったという。
室町時代になると、どういうわけか夷と三郎が混同され、夷三郎という一体の神と考えられるようになった。なんとも複雑なはなしである。
◆十日戎(えびす)の風習
西宮神社は海の守護神であったと同時に、鎮座するところは重要な交易地であったことから、次第に商売の神へと変化していく。
笹に米俵・小判・鯛・大福帳・打出小槌などをつけた福笹・吉慶・大宝または小宝と呼ばれる縁起物が売られ、これを神棚に飾っておき、 毎年新しいものと取り替えると福が授かるという。
かつては関東でも正月二十日に、戎講(えびすこう)と称して祭りを行う風習があったが、十日に祭るのは関西の風習である。
さて、神さまの役割というものはどんどん広がっていくもので、エビスには農業神としての顔もある。 大漁や商売繁盛の神なら方策をもたらしてくれてもおかしくない。そう考えられたのだろう。農村では、豊作をもたらす田の神の性格もかね、 田植えの初苗を供える例もみられる。
また山村では、山の神をエビスと呼ぶ所もあり、田の神と山の神が定期的に行き来するという考えとエビスの信仰が重ね合わされたものと考えられる。 これは外部から来訪し福をもたらすというイメージが、田の神・山の神の去来という全国的にみられる信仰と結びつけらたものと考えられる。
大黒天とエビスの二体を並べて、エビス大黒として祀ることが、室町時代中期ごろからあったようだ。
これも強引な結びつけで、夷三郎の三郎は大国主命の子であり、大黒天は大国主命と同じとされていたから、親子二体を並べれば御利益も倍になるという発想だろう。
|
|
|
神社の神々 知れば知るほど 1999年発行 実業之日本社 より転載
