冠 婚 葬 祭 豆 知 識
==================================================
--- 目 次 ---
★ 「お色直し」は"婚家の色に染まる"は間違い
式では、結婚という神聖な儀式を神に報告し、神と交わるため、純白で清浄な白無垢を着、
お色直しでは、神への報告を終え、俗人に戻って宴会を楽しむという意味です。
★ 玉串を奉りて拝礼(玉串拝礼)の仕方
玉串とはサカキの枝(寒い地方ではヒサカキ又はヒバの枝を代用)に、紙垂シデを取り
付けたものです。これはこの世が常磐木の如く永遠に栄え続くこと、また紙垂は神前に
お供えする品々(衣服など)を意味します。
即ち、祭員の前に進んで正座(立礼のときは直立。以下同じ。)し、
①右手で玉串の元の方を上から、左手で中程を下から支えて受け取り、胸高に持ちます。
②神前に進み出て正座し、玉串を右回りに廻して元の方を手前に、先の方をやや高め
にして神前に向けます。
③両手で元の方を持って、祈念をこめます。
④次に玉串を右回り廻しての元を神前に向け、机(玉串案のこと)の上に供えます。
次に拝礼します。
即ち、
①拝(深いお辞儀)を二回します。
②次に両手を胸高に合わせて祈念をこめ、二回拍手します。
③最後に拝を一回します。
備考〉
(1) 神社神道における拝礼の基準作法は、この「二拝二拍手一拝の作法」です。全国の
神社において行われます。
ただし、伊勢の神宮は八度拝、また出雲大社等それぞれ古い作法を伝えるところもあります。
(2) 必要により、玉串奉献を行わず、神拝詞等を奏上することもあります。
即ち、
①神前に進み出て正座し、拝を二回します。 ②神拝詞、奉告詞、祈願詞などを懐中から取り出して読み上げます。
③神拝詞等を懐中に納めてから、「二拝二拍手一拝」をします。
(3) なお、自分の座を立つとき、自分の座に戻ったとき、また神前に相対して正座した
とき、神前を退くときなど、そのときに軽くお辞儀をしますと丁寧な作法となります。
祈祷の時などに行う、玉串拝礼の作法を動画・坐礼でご紹介
玉串拝礼の作法を神社本庁 提供の動画(フラッシュ)でご紹介
★ 抹香での焼香のしかた
===== 立礼焼香 =====
(1)数珠は左手に持ち、房(ふさ)の部分が下に来るようにします。焼香台に進む前に、遺族・僧侶に
一礼してから焼香台の方に静かにすすみます。
(◎数珠は、仏教徒以外は持ちません。原則として数珠を持つ時は常に左手に持ちます)
(2)焼香台の3~4歩前で止まり、遺影(故人の写 真)と仮位牌を見つめてから、改めて台の一歩手前まで進みます。
ここで一度合掌します。
合掌の際は、 数珠を持った左手に、空いている右手を添えるようにして(または数珠を両手にかけて
…宗派によって異なります)手を合わせます。
(3)焼香台の右前にある抹香(粉末状の香)を、 右手の親指・人さし指・中指、の三本の指でつまみ、
頭を垂れるようにしたまま 目を閉じながら額のあたりの高さまで捧げます。
(4)額までかかげた手をおろしながら、抹香を静かに左側の香炉の中に落 とします。これを1~3回繰り返します。
(回数は宗派によって異なります)
人数が多く、混雑している時 は、1回だけ丁寧にたけば良いでしょう。
(5)焼香が済んだら、もう一度合掌します。
次に、遺影の方を 向いたまま3歩下がり、僧侶・遺 族に一礼をし、くるりと向きを変えて自分の席に戻ります。
焼香作法(仏式篇)をご紹介
===== 座礼焼香 =====
●基本的には立礼と同じですが、和室などで焼香するときに近い距離なら立ち上がらずに焼香台まで移動するやり方があります。
このときの移動の作法を、「膝行・膝退(しっこう、しったい)」と言います。
※膝行・膝退(しっこう、しったい)のやり方…腕の力で身体を少し持ち上げ、ひざをついたまま少しづつ移動します。
(1)親指だけを立てて、他の指を握ります。
(2)そのまま両腕を身体の両脇よりもやや前に置き、力を込めて身体を少し持ち上げるようにしながら、膝を少しずつ
前に出しながら移動します。
(3)遺族の席の前まできたら、遺族と僧侶に礼をします。座布団には、座らない方が良いようです。
焼香台の前まですすみ、座布団を下座へよけて、正座をします。
まずは一度ここで合掌します。
焼香は、立礼と同じように、親指、人さし指、中指の三本の指で抹香をつまみ、目を閉じて額の高さまでかかげます。
故人に礼をしながら、香炉に落とします(1~3回)。
最後に、両手をそろえて合掌します。
(回数は宗派によって異なります。人数が多く、混雑している時は、1回だけ丁寧に行えば良いでしょう。)
(4)焼香を終えたら、祭壇の方を向いたまま両腕を脇について、ひざを浮かせて後方に下がります。僧侶、遺族に
一礼をします。
(5)今度は、両脇に腕をつきながら、ひざで後退するようにして、自席にもどります。
※席が遠い場合には、(1)(2)については、腰をかがめた中腰の姿勢で遺族の前まで進みます。焼香を終え、
(4)で、僧侶、遺族に一礼を済ませてからは、中腰の姿勢で自席にもどります。
===== 回し焼香 =====
●狭い自宅などで葬儀を行なう場合、通常、祭壇に置かれている焼香台の代わりに、香炉、抹香などをお盆などに載せ、
前の方に並んでいる親族から順番に焼香していきます。
この場合、参列者は自分の席にすわったままで焼香することになります。
右側が抹香(粉末状のお香)、左側が香炉(火がついた小さな炭や灰などが入っているもの)です。
(1) 前の人から、お盆がまわってきたら、軽く一礼して受け取ります。
(2) 自分の膝の上か、すぐ前にお盆を置きます。
(3) 右手の親指、人さし指、中指の三本の指で抹香をつまみ、目を閉じて額の高さまでかかげます。
故人に礼をしながら香炉におとします。この動作を1~3回行ないます。(回数は宗派によって異なります。
人数が多く、混雑している時は、1回だけ丁寧に行えば良いでしょう。)
最後に、両手を揃えて合掌します。
(4)済んだら隣の人にまわします。このとき軽く一礼します。
★ 結婚スピーチのタブー
■忌み言葉
終わる・切る・切れる・破れる・別れる・離れる
出る・出す・戻る・去る・帰る・帰す・返る・飽きる
滅びる・苦しい・壊れる
とんだこと・とんでもない・なおまた・ではまた
かさねがさね・皆々様
別れや終わり、結婚が一度では終わらないなどと言ったことを連想する忌み言葉は結婚式の言葉として避ける。
★ 焼香の仕方
法要のときは、一般に線香ではなく焼香をつかいます。
焼香には、焼香台へ進み出て行う場合と、自分の席で行う「回し焼香」の二通りがあります。
宗派により焼香の仕方が違いますが一般的作法として、順番が来たら、施主に一礼して焼香台の前に進み、本尊、遺影、位牌を仰ぎ合掌礼拝します。右手で香をつまんで額のところまで押しいただきます。(浄土真宗では押しいただきません)香炉に静かにくべ、数珠を手に合掌礼拝します。最後に施主に一礼して席に戻ります。
線香をつかう場合も、宗派によって本数や供え方が違います。浄土真宗は線香を立てずに、適当な長さに折って寝かせます。
| 宗派 | 焼香の回数 | 線香の本数 |
| 天台宗 | 1回または、3回 | 3本を立てる |
| 真言宗 | 3回 | 1本を立てる |
| 浄土宗 | 1回または、3回 | 1本を立てる |
| 浄土真宗本願寺派 | 1回(額におしいだかず) | 折って寝かせる |
| 真宗大谷派 | 2回(額におしいだかず) | 折って寝かせる |
| 曹洞宗 | 2回(1回目は額に、2回目はおしいだかず) | 1本を立てる |
| 臨済宗 | 1回または、3回 | 1本を立てる |
| 日蓮宗 | 1回または、3回 | 1本を立てる |
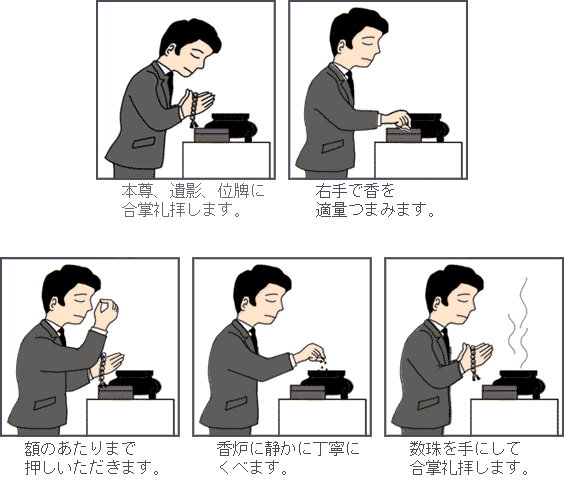
遺族(喪主側)・親族が向かって右側・親族は左側に友人他会葬者は焼香台の後ろ側に着座していることが多いです。まず焼香台近辺まで進み、右(遺族・親族)、左(親族)、後(友人他会葬者)にかるく礼をし、焼香台まで進みます。
- 遺影をご覧になり、合掌し礼をします。
- 右手でお香をつまみます。(会葬者が大勢の時には少しだけつまみます。)
- 額のところまで香を押しいただくのですが、浄土真宗はおしいただきません。また曹洞宗も2回目はおしいただきません。
- 香炉に香をくべます。宗派で決められた回数をくべるのですが、会葬者が多い場合1回だけの指定がある場合があります。
- 最後にもう一度遺影をご覧になり、気持ちを込めて合掌します。後ろ向きで三歩後退します。
もう一度左右に礼をし、退きます。
★ 合掌
日本人はお寺や神社の前では自然と手を合わせています。人に何かを強く頼むときも手を合わせてお願いします。「合掌」は日本人の生活にしっかりと根付いています。
いまさら言うまでもなく、両方の手のひらを胸あたりの前で合わせることを「合掌」といいます。
合掌はインドの礼法ですが、仏教徒が礼拝の方法として用いたことから仏教の作法となり、日本に伝わりました。
仏教では、右手は仏(ほとけ)の世界、左手は衆生(しゅじょう)の世界をあらわすといわれています。衆生とはすべての生き物をさしています。右手と左手を合わせて合掌することで、仏と衆生が一体になる意味があるのです。
合掌の仕方は、一般には、胸の前で右と左の掌と指をピタリと合わせ、指先が斜め上を向いた形にします。その形にしたら、軽く目を閉じて、頭を30度くらいの角度で下げます。
法要のときは、手に数珠をかけて何度も「合掌」をします。戸惑わないように、普段からおまいりの習慣をつけておくとよいでしょう。
★ 数珠の扱い方
数珠は葬式や法事など仏事には欠かせません。必ず、一人に一つは持つものです。
数珠の玉の数は人間の煩悩(ぼんのう)をあらわす百八個が基本となっています。常に携帯して手を合わせれば、煩悩が消え、功徳(くどく)を得るといわれています。
正式な数珠は宗派によって、数珠の形が違っています。一般には各宗派共通で使える略式の数珠が使われています。略式の数珠は、18~43個くらいの珠で作られていて、数に決まりはありません。
珠の素材に宗派による違いはないので、好きなものを選んでよいでしょう。
尊いといわれているのが菩提樹の実です。お釈迦さまが悟りを開かれたという場所にあった木が菩提樹だからです。木の実は年が経てば経つほど、つやを増してきます。紫檀や黒檀などの銘木の数珠もあります。
宝石の数珠もあります。水晶、メノー、ヒスイ、サンゴ、オニキスなどがあります。特に水晶は、数珠に使われる代表的な珠で、仏教で言う七宝のひとつに数えられています。
数珠の扱い方は、数珠を左手にかけて右手を添えるように合わせるか、合わせた両手にかけ親指で軽く押さえて、合掌します。
どんな素材の数珠でも使ったあとは、やわらかい布などで軽く拭くだけにして、水洗いや薬品を使うのは避けてください。使わないときは数珠袋や桐箱、紙箱に保管しておきましょう。
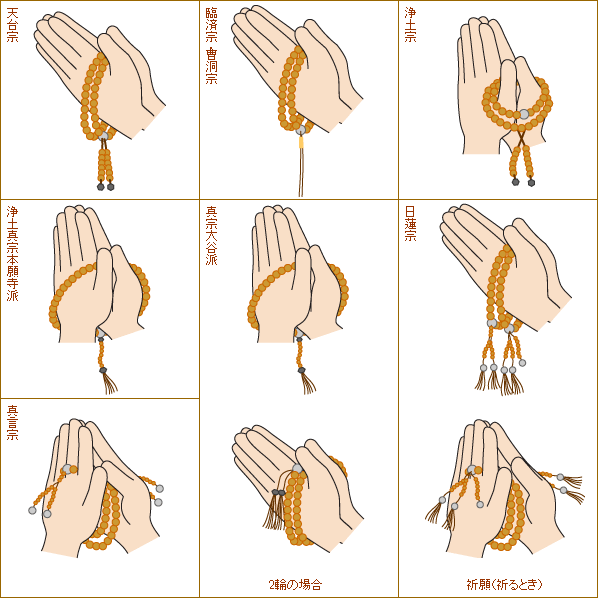
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
★結婚記念日呼称
1周年:紙婚式
2周年:藁婚式、綿婚式
3周年:革婚式、糖果婚式
4周年:花婚式、(絹婚式)、皮婚式(皮革婚式)、書籍婚式
5周年:木婚式
6周年:鉄婚式
7周年:銅婚式
8周年:青銅婚式、ゴム婚式、電気器具婚式
9周年:陶器婚式
10周年:アルミ婚式、錫婚式
11周年:鋼鉄婚式
12周年:絹婚式、亜麻婚式
13周年:レース婚式
14周年:象牙婚式
15周年:水晶婚式
20周年:磁器婚式、陶器婚式
25周年:銀婚式
30周年:真珠婚式
35周年:珊瑚婚式
40周年:ルビー婚式
45周年:サファイア婚式
50周年:金婚式
55周年:エメラルド婚式
60周年:ダイヤモンド婚式
75周年:プラチナ婚式
★太巻き寿司
 太巻き寿司は、古くから冠婚葬祭や集まりの時のごちそうとして受け継がれ、千葉の郷土料理を代表するものです。そのルーツは諸説ありますが、
太巻き寿司は、古くから冠婚葬祭や集まりの時のごちそうとして受け継がれ、千葉の郷土料理を代表するものです。そのルーツは諸説ありますが、
「具を芯にして巻く」という技法が原点になって、その時代の農産物や海産物などの食材を活かして冠婚葬祭や地域の集まりで作られ、家庭のなかでも伝えられてきました。
のりや焼き卵で巻いた直径約8cmのご飯の中に、ゴボウやカンピョウなどで「祝」「志」の文字をかたどることが多い。季節の花や鳥、風景を描くこともあり、華やかに食卓を彩る。
冠婚葬祭などで振舞われる料理の一つで、江戸時代、紀州の漁師が房総沖まで漁にでる際、長い航海で弁当が腐らぬよう、飯に酢をまぜていたものが原形という説がある。
太巻きすしの参照URL
千葉の郷土料理(太巻き寿司)
千葉房総郷土料理:太巻き祭り寿司
★ 四十九日の忌明け(きあけ)◇
身内が死亡すると、死の汚(けが)れが身についているとして、遺族は行動を控えるのが習わしです。
この期間を「忌中(きちゅう)」「中陰(ちゅういん)」といいます。
仏教では、死後四十九日までを忌中とし、この間は7日ごとに7回の法要(法事)が営まれます。
浄土真宗を除く、仏教ではお亡くなりになられると、ご逝去された日を1日目と数え、7日毎に裁判を行います。
●1回目~初七日(しょなのか)法要(法事)/7日目
----------------------------------------------------------------------------
現在では葬儀の当日にいっしょに済ませることが多くなっています。
本来は死後7日目に行うものですが、遠方から足を運んでくれた人の便宜を図って、
当日に繰り上げて行うことも多くなってきています。
会場も、自宅にかぎらず、ホテル・料亭・会館などを利用するケースが増えています。
別日に行う場合は、近親者や親しい友人・知人を招き、僧侶に読経をあげてもらい、茶菓や精進料理でもてなします。
●2回目~二七日(ふたなのか)/14日目
3回目~三七日(みなのか)/21日目
4回目~四七日(よなのか)法要(法事)/28日目
----------------------------------------------------------------------------
僧侶は招かず、身内だけで供養するか省略することが多くなっています。
省略するにしても、忌中の期間中は線香やろうそくの火をできるだけ絶やさないようにします。
●5回目~五七日(いつなのか)法要(法事)35日目
----------------------------------------------------------------------------
死後35日目を忌明(きあけ)けとする宗派では、僧侶と近親者を招いて、初七日と同様に手厚く供養します。
●6回目~六七日(むなのか)法要(法事)42日目
----------------------------------------------------------------------------
僧侶は招かず、身内だけで供養するか省略することが多くなっています。
●7回目~七七日忌(しちしちにちき・なななぬかき)(四十九日)法要(法事)/49日目
----------------------------------------------------------------------------
忌中の最後の日を、「満中陰(まんちゅういん)」 といい、この日で忌明けとなります。
僧侶をはじめ親族や故人の縁者を招いて、盛大に法要(法事)を営み、
その後、埋骨式(納骨式)を行うのが一般的です。
そして、これまでの白木の位牌を菩提寺に納め、黒塗りか金箔の位牌に替えて、
通夜から閉じたままになっていた仏壇を開いて安置します。
この日は 「お斎(おとき)」 という会食の席を設けて、僧侶と参列者をもてなします。
★ 香典袋の書き方
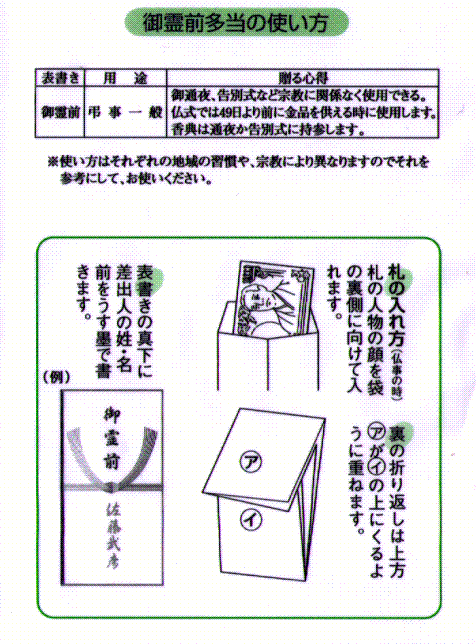 |
|
★ のし・のし袋
| 「のし」は正式には「のしあわび」といい、昔、貝のアワビをのして使った事から、こう呼ばれるようになりました。 のし袋やのし紙の表書きは、毛筆、又は筆ペンを使ってバランス良く丁寧に。 水引の結び方には一度結んだらほどけない「結びきり」と、ほどいて何度も結ぶことのできる結び方の「蝶結び」があります。 [結びきり]は結婚、お悔やみごと のように二度とくり返してはいけないことに使い、 [蝶結び]は何度もくり返してよい一般 的な祝い事に使います。 のし袋は、奉書紙や半紙を用いて手作りの包みを作ることもできます。 その場合慶事なら2枚、弔事なら1枚の紙を使いますが、慶事と弔事では折り方が逆になります。 慶 事 中包みを紙の中央に置き、** 左・右 ** の順で折り、下側を上側にかぶせる。 弔 事 中包みを紙の中央に置き、** 右・左 ** の順で折り、上側を下側にかぶせる。 |
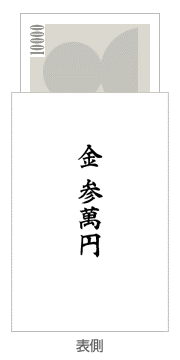 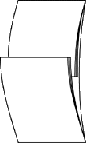 |
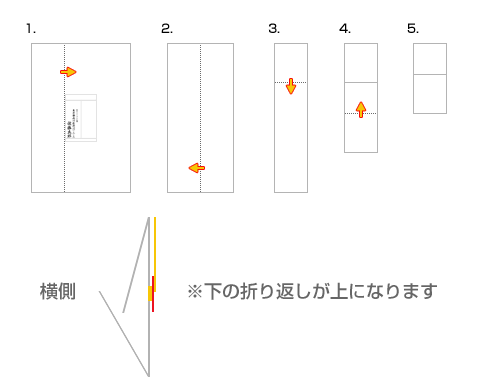 |
|